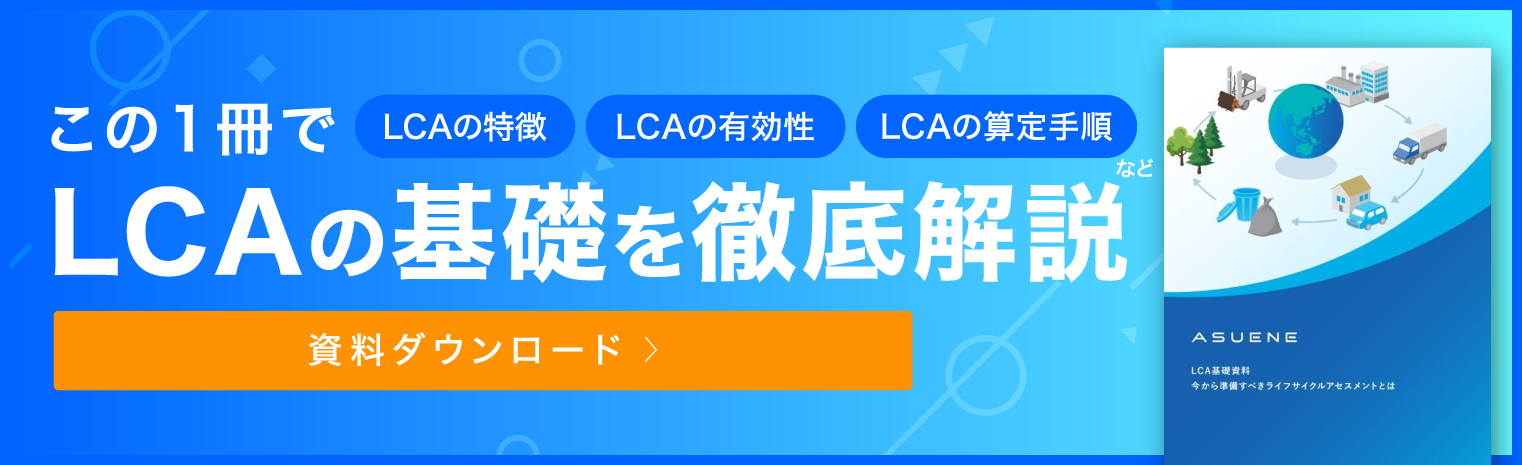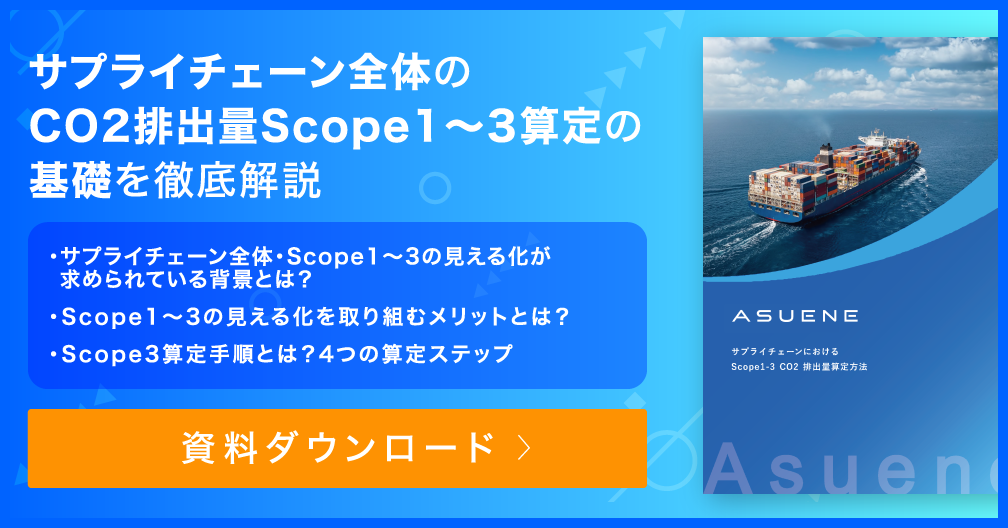世界の発電方法や自給率とその特徴。国によって異なる電力事情とは
- 2024年01月31日
- 発電・エネルギー

2050年までのカーボンニュートラル達成に向け、日本は再生可能エネルギーの導入を促進し、同時にエネルギー自給率の向上を目指しています。そして、日本だけでなく世界各国でも、化石エネルギーから再生可能エネルギーへの移行が急速に進んでいます。
しかし、現在日本はほとんどのエネルギー源を輸入に頼っています。もし海外でなにかの問題が生じて資源を輸入できなくなると、エネルギー源を確保できなくなるという大きな弱点を抱えていることになります。
世界の主要国と日本の発電方法、自給率などを把握し、エネルギー問題や企業の経営への影響について考える材料にしましょう。
目次
-
世界各国の電力供給における発電方法の比率
-
世界各国における発電方法の特徴
-
世界各国の電力自給率
-
まとめ:再生可能エネルギーの導入で、社会課題解決へ貢献しよう!
1. 世界各国の電力供給における発電方法の比率
グローバルな視点で見ても、発電方法において最も利用されているのは石油や石炭などの化石燃料です。温室効果ガス削減の観点からは再生可能エネルギーの普及が望ましいのですが、太陽光や風力などの発電手段はまだそれほど広がっていません。世界の電力供給手段について解説します。
世界の電源構成
世界の電源構成をエネルギー源別に見てみると、石油が2019年時点で31.0%と、依然として最も多いことがわかります。石油消費量は1965年から2021年にかけて年平均1.9%で増加しました。
次に高いのが全体の26.9%を占める石炭です。2000年代に安価な発電用燃料として消費が拡大した石炭ですが、中国の需要の伸びが鈍ったことや、アメリカで天然ガスへの代替が生じたことなどから、2015年以降は消費が減少する年もありました
石油・石炭以上に消費量が伸びたのが、全体の24.4%を占める天然ガスです。天然ガスは気候変動への対応が強く求められる先進国を中心に、発電用・都市ガス用に消費が伸び、年平均3.2%増加しています。
伸び率で見ると近年増加しているのが、原子力と太陽光・風力などによる再生可能エネルギーです。しかし2021年時点で全体に占める割合は原子力が4.3%、再生可能エネルギーが6.7%と、まだ大きなシェアとは言えません。
しかし、太陽光発電や風力発電は近年コストが低下しており、市場での競争力があがっています。世界が循環型経済・脱炭素社会を目指す中、さらに再生可能エネルギーの比率は拡大していくと予想されます。

出典:資源エネルギー庁『令和4年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2023)』
世界の化石燃料(石炭)への依存度
世界の化石燃料への依存度を、代表的な石炭を例に見てみましょう。世界の石炭生産量は2000年代に入り急速に拡大しました。
2000年には46億3799万トンであった石炭の生産量は、2021年には78億7674トンとなっています。世界の石炭消費は、2000年から2013年まで中国やインドなどを中心に増加、その後は増減を繰り返しましたが、2021年の石炭消費量は79億5812万トンで、新型コロナウィルスの影響から減少した2020年対比で4億4742万トン増となっています。

出典:資源エネルギー庁『令和4年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2023)』
2.世界各国における発電方法の特徴
発電方法の内訳には国によって違いがあります。日本では石炭をはじめとする化石燃料による発電の占める割合が高いですが、そうではない国もあります。各国における発電方法の特徴について解説します。

出典:資源エネルギー庁『令和4年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2023)』
アメリカ
2000年代前半、アメリカで地下2000mに存在するシェールガス(従来手法では採掘の難しい、頁岩(シェール)に含まれている天然ガス)を掘削する技術革新が起こりました。エネルギー源としてシェールガスの生産が本格化したことは「シェール革命」と呼ばれ、世界のエネルギー事情に大きな影響を与えました。
アメリカでの発電は石炭が20.2%、天然ガスが39.6%、水力・原子力・再生可能エネルギーを合わせた非化石エネルギーの割合が39.3%と、大きく3つに支えられています。そのうち石油での発電はわずか0.9%です。
出典:資源エネルギー庁『2018年5月、「シェール革命」が産んだ天然ガスが日本にも到来』(2018/6/12)
出典:資源エネルギー庁『令和4年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2023)』
イギリス
イギリスは国内の豊富な石炭による石炭火力が発電方法のメインでしたが、北海ガス田の開発に伴いガス火力の比率が増加したこと、およびCO2価格が引き上げられたことにより、石炭火力の割合が2.1%にまで低下しました。
イギリスでは石炭・石油・天然ガスを合わせた化石エネルギーの割合が38.5%、水力・原子力・再生可能エネルギーを合わせた非化石エネルギーの割合が61.6%と、非化石エネルギーの割合が化石エネルギーの割合を上回っています。今後もイギリスでは増え続ける電力需要を補うために、再生可能エネルギーの導入が進められる方針です。
出典:資源エネルギー庁『令和4年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2023)』
出典:資源エネルギー庁『2050年カーボンニュートラルに向けた課題と取り組み』p.37
フランス
フランスの電力供給で特徴的なのは原子力が67.1%と大きな割合を占めていることです。このためフランスの化石エネルギーの割合は2020年の時点ですでに8.7%です。このように原子力発電の比率が高いのは、オイルショックを受けてエネルギー自給率を引き上げるために原子力発電を推進したことが背景となっています。
アルプス山脈などによる水資源にも恵まれたフランスは、水力発電も11.8%を占めています。東京電力福島第一原子力発電所事故以降は原子力発電の比率を2035年までに50%まで引き下げる方向へ舵を切っており、その分再生可能エネルギーの割合を増やす方針です。しかし再生可能エネルギーは天候によって発電量が左右されることなどから、原子炉の停止などは当初予定より遅れています。
出典:資源エネルギー庁『『パリ協定』のもとで進む、世界の温室効果ガス削減の取り組み⑥』(2019/6/20)
出典:資源エネルギー庁『令和4年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2023)』
ドイツ
ドイツでは2023年の上半期に、電力消費量の50%以上が自然エネルギーの電力で供給されました。さらに2030年までに電力消費量の80%を自然エネルギーで供給し、2035年までに国全体の電力を完全に脱炭素化するという目標がドイツでは掲げられています。ドイツは2023年4月15日に原子力発電のフェーズアウト(段階的撤廃)が完了しており、その代わりに周辺諸国から再生可能エネルギーによる発電電力を輸入するようになったのです。
2009年に58.9%を占めていた化石エネルギーの割合は2020年には43.0%に、2009年に23%を占めていた原子力は2021年には11.4%に減少しています。一方で2009年に14.9%であった再生可能エネルギーは2020年には42.4%まで増加しました。
出典:自然エネルギー財団『ドイツに見る原子力発電フェーズアウトの効果』(2023/7/23)
日本
資源の乏しい日本では、石炭・石油・天然ガスを合わせた火力発電の占める割合が7割以上と、他の主要国と比較して大きくなっています。さらに日本は島国であるため、他国で発電した電気を直接購入することはできず、燃料を輸入した上で日本国内で発電しなければならないという特徴も持っています。
今後は原子力を一定規模で活用しつつ、2050年には再生可能エネルギーの主力電源化を目指します。同時に水素・アンモニアの火力への活用のための技術開発も進められています。
出典:資源エネルギー庁『2050年カーボンニュートラルの実現に向けた検討』p.6,13,16
3.世界各国のエネルギー自給率
電力供給に大きく関わってくるのが、エネルギーの自給率です。エネルギーの自給率が低ければ、電力の多くも輸入に頼ることとなります。各国のエネルギー自給率について解説します。

出典:資源エネルギー庁『日本のエネルギー 2022年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」』
アメリカ
アメリカではシェール革命により原油と天然ガスの国内生産量が2000年代前半以降に増加しました。また、気候変動問題を重視するバイデン大統領就任により、再生可能エネルギーの導入量も増加しています。
2019年時点でアメリカのエネルギー自給率は104.2%と、2007年から比較して大きく向上しています。アメリカの自給率はしばらくはこのような高い水準が続くと予想されます。
出典:資源エネルギー庁『グラフで見る世界のエネルギーと「3E+S」安定供給① ~各国の自給率のいま』
イギリス
イギリスでは北海油田が開発され、1980年頃にはエネルギー自給率が100%を超えました。北海油田からの原油・ガスの生産で、イギリスは一時エネルギー輸出国となりました。しかし、北海油田の枯渇により原油の生産は徐々に減少し、それに伴いエネルギー自給率も下がりました。
2014年頃には60%を下回ったイギリスのエネルギー自給率ですが、その後の原子力発電の開発などにより、再び回復傾向となりました。イギリスのエネルギー自給率は2019年時点で71.3%です。
出典:資源エネルギー庁『グラフで見る世界のエネルギーと「3E+S」安定供給① ~各国の自給率のいま』(2019/7/9)
フランス
フランスのエネルギーに関しては、エネルギーの中でも特に電力の7割以上が原子力によって供給されているという特徴があります。原子力発電は、海外からの燃料調達が途絶えた場合でも国内に保有する燃料でけで数年に渡ってエネルギー供給が維持できます。このように発電における原子力発電の割合が高いことにより、フランスの電力自給率は50%前後で安定して推移しています。
出典:資源エネルギー庁『グラフで見る世界のエネルギーと「3E+S」安定供給① ~各国の自給率のいま』(2019/7/9)
ドイツ
ドイツのエネルギー自給率は40%前後で少し減少しながら、ほぼ横ばいの推移です。かつて国内の電力の大部分を供給していた石炭による火力と原子力を減少させ、代わりに再生エネルギーを導入することにより、結果として自給率の推移はほぼ同じ水準を保っています。
ドイツは2023年に原子力発電を全て廃止しており、さらに2038年までに石炭火力を段階的に廃止する方針です。今後も再生可能エネルギーの導入は促進されますが、国内の電力自給率の多くの割合を支えている石炭と原子力の減少も進むため、ドイツの電力自給率自体はこのまま横ばいで推移すると考えられます。
出典:資源エネルギー庁『グラフで見る世界のエネルギーと「3E+S」安定供給① ~各国の自給率のいま』(2019/7/9)
出典:資源エネルギー庁『今後のエネルギー政策について』p18,19(2023/6/28)
日本
2011年に東日本大震災が起こる以前の日本のエネルギー自給率は20%前後の水準でした。東日本大震災以降、原子力の発電量が減少し一時は自給率が6%まで落ち込みました。
2020年時点での日本のエネルギー自給率は11.3%です。2012年の「固定価格買取制度(FIT)」導入による再生可能エネルギーの増加や原子力の再稼働などにより自給率は少しずつ高まっています。

出典:資源エネルギー庁『日本のエネルギー 2022年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」』
出典:資源エネルギー庁『グラフで見る世界のエネルギーと「3E+S」安定供給① ~各国の自給率のいま』
出典:資源エネルギー庁『2021—日本が抱えているエネルギー問題(前編)』(2022/8/12)
4.まとめ:再生可能エネルギーの導入で、社会課題解決へ貢献しよう!
世界各国の発電割合はその国の政策や事情を反映しています。ただし電力自給率に着目してみると、世界の主要国がいずれも4〜5割のエネルギー自給率を維持しているのに対し、日本では電力自給率が1割程度と際立って低いことがわかります
2050年カーボンニュートラルを目指し再生可能エネルギーの導入を推し進めることは、同時に現在の日本の低いエネルギー自給率の改善にもつながります。日本の国際的な競争力の強化、経済の長期的な成長、企業のサプライチェーンの生き残りなど、再生可能エネルギー導入は社会を好循環に導くために重要な鍵です。
国際的にも急速に再生可能エネルギーの導入が進んでおり、今後は再生可能エネルギーの導入コスト低下や市場での競争力の強化が期待できます。日本の企業各社も自社への再生可能エネルギー導入を検討・実行し、環境問題やエネルギー問題などの社会課題解決へ貢献しましょう。