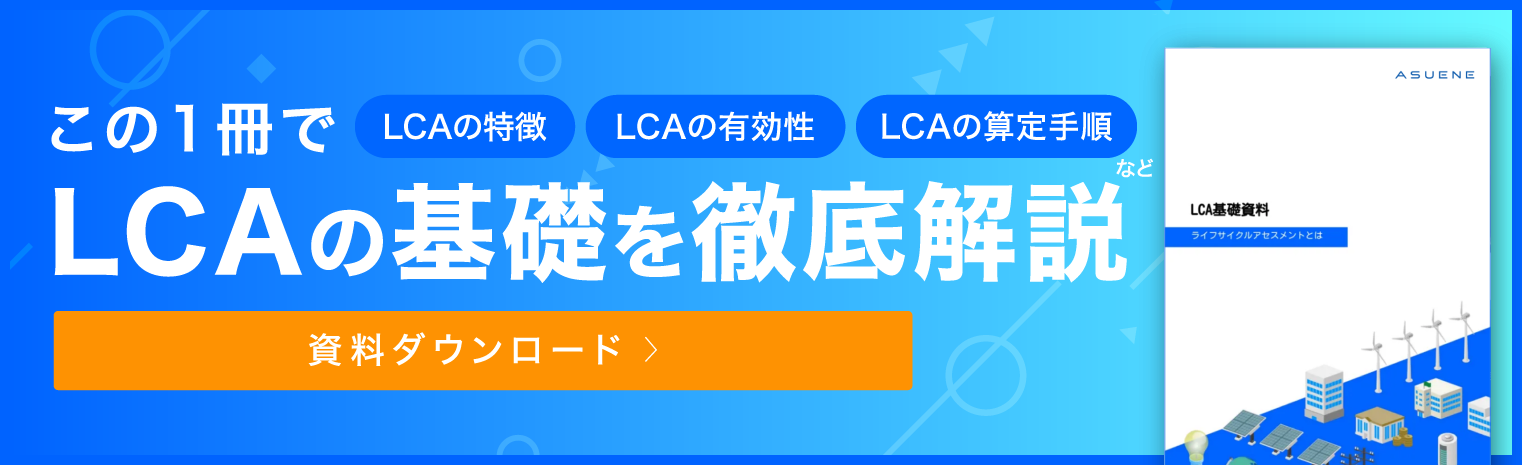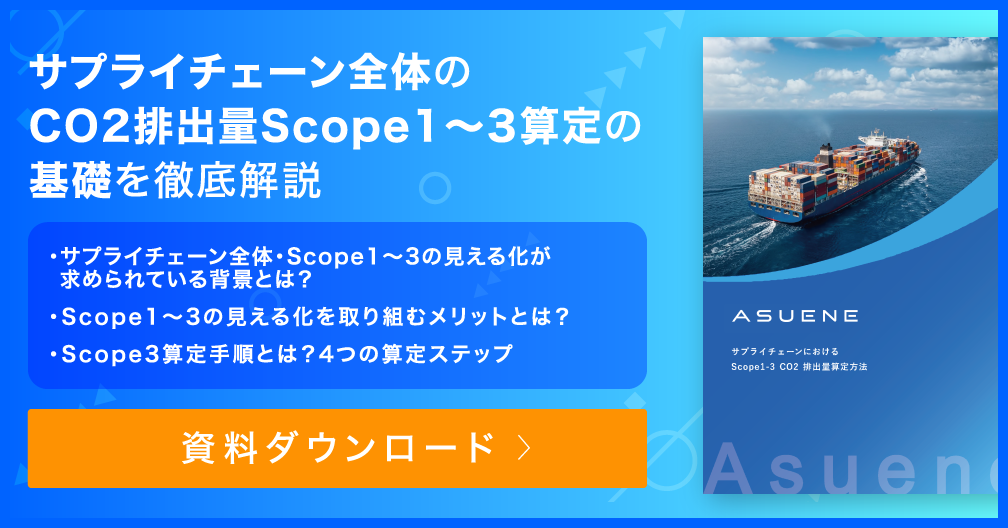気候変動で雨はどうなる?地球温暖化と豪雨の関係とは
- 2022年06月15日
- 環境問題

世界や日本では気候変動によるさまざまな異常気象が起きており、これまでは何十年に一度と言われていた規模の災害が頻発しています。中でも雨による災害は各国で増えており、豪雨による土砂崩れや冠水や洪水の被害は甚大です。このような異常気象を引き起こす気候変動は地球温暖化現象と無縁ではありません。日本と世界に気候変動が及ぼす影響と、それに伴い変化している雨の状況を解説していきます。
目次
-
地球温暖化がもたらす気候変動
-
気候変動による豪雨傾向と異常気象
-
気候変動で世界と日本の雨はどうなる?
-
気候変動と雨の変化に対する日本と世界の取り組み
-
まとめ:気候変動を抑制し本来の“恵みの雨”を取り戻すためにできること
1. 地球温暖化がもたらす気候変動
温室効果ガス排出と地球温暖化の関係
温室効果ガスとは二酸化炭素(CO2)をメインとしたメタン・一酸化二窒素・フロンガスなどを指します。温室効果ガスには海や陸などの地球の表面から地球外に向かう赤外線を大気にとどめ熱として蓄積し、それを地表に戻すという性質(温室効果)があり、それが地表の大気を温め多様な生物が繁栄する環境を生み出します。
しかし温室効果ガスの濃度が高まり過ぎると、地表の温度が過度に上昇してしまい、大気の温室効果が強まり、それが地球温暖化の原因になっていると考えられています。人間の経済活動による大量の化石燃料使用や森林の減少などで20世紀に入ると急速に温室効果ガスの排出は増加しました。
出典:環境省「気候変動の国際交渉 世界のエネルギー起源CO2排出量(p.1)(2018)
温暖化がもたらすのは気温上昇だけではない
温暖化というと気温の上昇だけが注目されがちですが、問題は気温上昇だけではありません。大気中に増える温室効果ガスは太陽からくる熱の流れを変え、大気の循環を変化させてしまいます。その結果、地球の地上付近では気温が上昇して「温暖化」を発生し、その結果地球全体の気候を大きく変化させてしまう「気候変動」を生むのです。
2. 気候変動による豪雨傾向と異常気象
一日あたりの強い雨は増加しているのに降水日は減少?
日本では一日あたりの雨の降水量が100ミリや200ミリ以上になる大雨の日がこの100年ほどで増えていると言われています。しかし、このように一時間に50ミリ以上降る豪雨の日もある一方で、年間の降水日はどんどん減少しています。今後温暖化が進めば2050年頃には全国の8割の地域では短時間の大雨の発生回数が増加すると考えられており、「降らないときは全く降らないのに、降るときは大量に降る」という降雨の構図になりつつあります。
出典:国土交通省「気候変動の影響について」(p.2)(2019.11.22)
出典:日本気象協会「(SDGs レポートVol.5)気候変動で増える雨の災害に備える 〜求められる実効性の高いBCP対策~」
雨だけではない気候変動による異常気象
また気候変動による異常気象は雨だけではありません。台風にも影響を及ぼしています。日本は台風の多い国ですがその台風の移動速度が温暖化の影響により遅れているのです。台風の速度が遅れるということは、台風が通り抜けるまでの時間が長くなるということです。そうなれば当然雨と風の被害がそれだけ甚大になるのは避けられません。このまま温暖化が進めば今世紀末には、⽇本の位置する中緯度帯では接近する台⾵(熱帯低気圧)の移動速度は10%遅くなると考えられています。
出典:気象庁気象研究所「【共同プレスリリース】地球温暖化によって台風の移動速度が遅くなる」(2020.1.8)(p.5)
気候変動に伴う降雨量や洪水発生頻度は
今後もし、温暖化が進み気温が2度上昇した場合、気候変動に伴い、日本の降水量は約1.1倍になり、それにともない洪水の確率は約2倍になると予測されています。気候変動による豪雨の増加により、相対的に安全度は低下する一方で氾濫危険水位(河川が氾濫する恐れのある水位)を超過した河川数は、増加傾向となっています。
出典:国土交通省「気候変動の影響について」(p.4)(2019.11.22)
3. 気候変動で世界と日本の雨はどうなる?
世界と日本の降水量の変化
(1)世界
世界の年間降水量は地球全体では一様な変化傾向は見えませんが、地域によって年間降水量が増加する地域と減少する地域があり、北米やヨーロッパでは1901年以降は降水量が増加する傾向が見られています。また高緯度の地域や太平洋赤道、中緯度の湿潤地域で年平均降水量が増加する傾向が指摘され、一方では中緯度と亜熱帯の多くの乾燥地域では降水量が減少する可能性が高いと予測されています。
出典:環境省「気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート2018~日本の気候変動とその影響~」(p.37)(2018.2.16)
(2)日本
日本の梅雨の時期から夏期の雨は、このまま地球温暖化が進むと梅雨前線の北上が遅くなり、太平洋側から西日本では6月の一日の平均降水量が減少、7月には日本列島で一日の平均降水量が増加するという傾向が見られています。しかし降水量の減少が見られる 6月の西日本においては、一日の降水量が平均としては減少しますが、短時間に200ミリを超えるような大雨は逆に増えると予測されているのです。
出典:環境省「気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート2018~日本の気候変動とその影響~」(p.37)(2018.2.16)
熱帯低気圧の最大風速及び降雨量は増加する可能性がある
地球全体での熱帯低気圧(熱帯の海上で発生する低気圧)の発生頻度は減少、もしくは変化がない可能性が高いのですが、平均した熱帯低気圧の最大風速及び降雨量は増加する可能性が高いと考えられています。しかし地域別の予測の確信度は低いとなっているので今後の研究結果が待たれます。
一方ハワイを中心とした東部から中部北太平洋域では低気圧は増加すると考えられており、日本の南海上からハワイ近郊及びメキシコの西海上では強烈な台風が増加する可能性が高くなっていま
出典:環境省「気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート2018~日本の気候変動とその影響~」(p.57)(2018.2.16)
各国の豪雨と干ばつ被害
IPCC(気候変動に関する政府間パネル)により、1950年以降、世界の殆どの地域は地球温暖化による異常気象の影響を受けたと報告されました。IPCCは世界を45のエリアに分類し、高温地域は全大陸の41地域に達し、大雨はアジアや欧州など19の地域、干ばつはアフリカなど12の地域で増加したと伝えました。また日本を含む東アジアで猛暑日や豪雨、干ばつが増加していることも報告されました。
報告書には「温室効果ガスの濃度増加は、人間活動によって引き起こされたことに疑う余地がない」「人為起源の気候変動は、世界中の全ての地域で、多くの気象及び気候の極端現象に既に影響を及ぼしている」と、人類の温室効果ガス排出が地球温暖化を引き起こした要因の一つであると明確に記載されたのです。
出典:環境省「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書(AR6)サイクル」(2021.8.9)
4. 気候変動と雨の変化に対する日本と世界の取り組み
温室効果ガス排出を削減する努力・カーボンニュートラル
このまま温室効果ガスの排出が続けば、地球温暖化による気候変動は加速していくでしょう。そうならないためにも私たちは温室効果ガスの削減に努めなくてはいけません。世界各国では温室効果ガスを削減する努力が始まっています。その一つが「カーボンニュートラル」です。カーボンニュートラルとは「温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること」であり、CO2をはじめとする温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするという取り組みです。
日本では「2050年カーボンニュートラル宣言」が行われ、再生可能エネルギーをはじめとしたCO2フリー電気の利用など多彩な取り組みが始まっているのです。
出典:環境省「脱炭素ポータル」
世界で進む気候変動適応策
温室効果ガス削減とともに加速する気候変動の影響に対して適応する対策も世界では始まっています。パリ協定では2020年以降、国際社会が気候変動対策にどう取り組むかが規定されました。パリ協定には
-
気候変動の悪影響に適応する能力並びに気候に対する強靱性。
-
食糧の生産を維持しつつ温室効果ガスについて低排出型の発展を促進する能力を向上させること(以上二条から)
等の世界全体の目標が掲げられています。そしてパリ協定では2023年以降、5年ごとに協定の目的と長期目標達成のために、世界全体で気候変動対策がどれくらい進んでいるかを評価することも定められました。これにより世界各国は自国の環境適応策を次々と推し進めることになりその対策が進んでいます。
日本の「気候変動の影響への適応計画」
日本では気候変動への適応を推進することを目的に平成30年6月に気候変動適応法が制定され、それに基づき、平成30年11月27日に「気候変動適応計画」が閣議決定されました。「あらゆる関連施策に気候変動適応を組み込む」「地域の実情に応じた気候変動適応を推進する」等の7本の基本戦略がたてられ、それをもとに関係府省庁が緊密に連携して気候変動適応を推進することとなったのです。
5. まとめ:気候変動を抑制し本来の“恵みの雨”を取り戻すためにできること
温室効果ガス排出によって気温が上昇し大気が不安定になりそれによって気候変動が誘発されます。気候変動の影響で本来は私たちに恵みをもたらすはずの雨が、近年は大きな災害の原因になっているのです。このまま温暖化が進めば今後も予測のできない異常気象が起きる可能性が高まるでしょう。
持続可能な社会と地球環境を維持するためにも、企業は温室効果ガスの排出削減を目指す努力をする必要があります。気候変動を少しでも抑制し温暖化から地球を守る努力をしてみませんか。