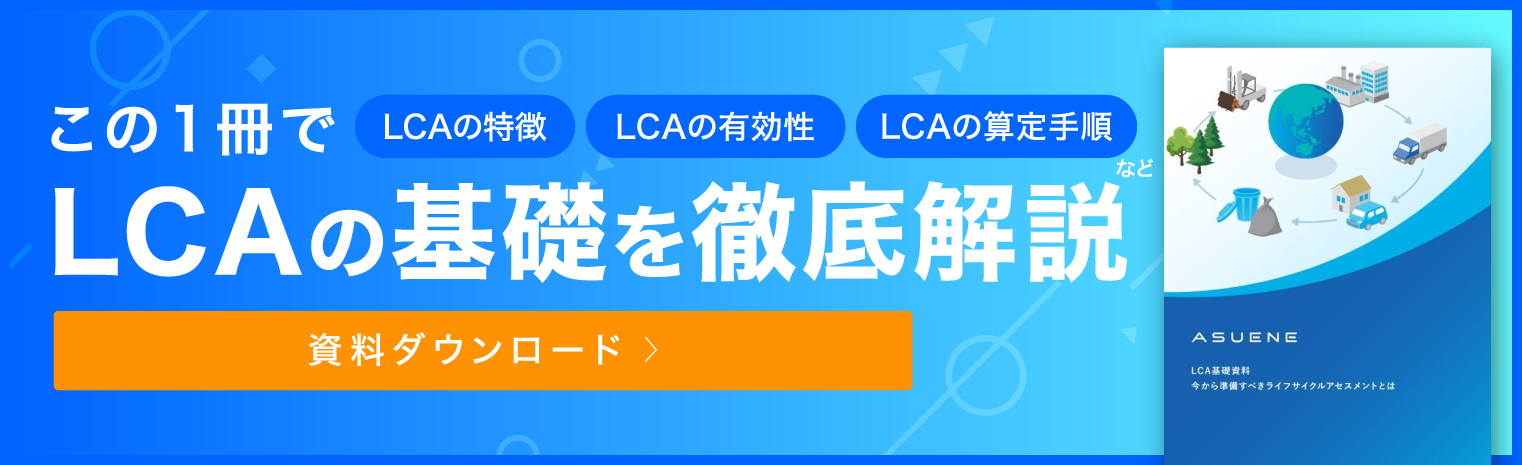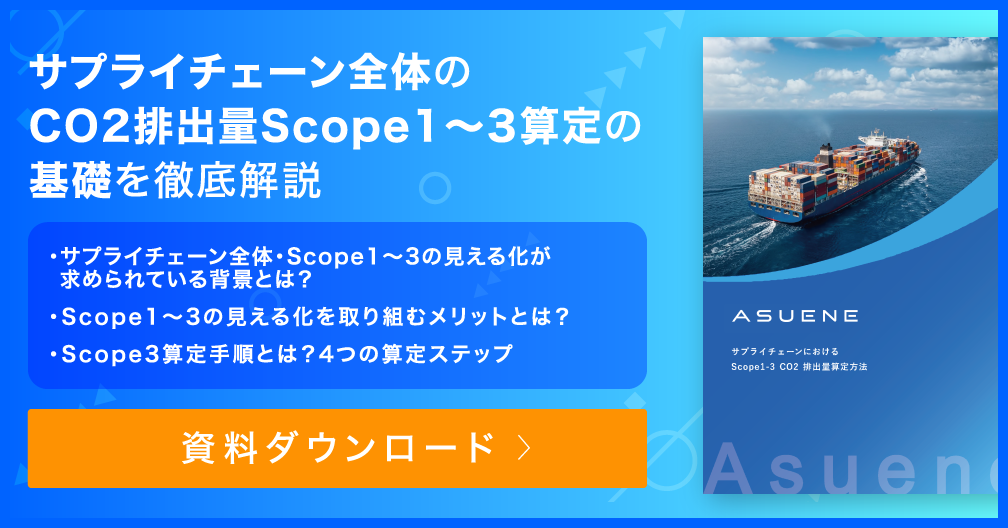工場における省エネ対策とは?実際の取り組み事例も紹介
- 2024年05月29日
- 発電・エネルギー
工場における省エネ対策について、わかりやすく解説します。工場では製品の製造などで、大きなエネルギーを必要とします。環境対策が地球規模で大きな課題となっている中、工場でも省エネ対策が不可欠です。
本記事では工場における省エネルギーの必要性や対策の方向性について触れたうえで、実際の企業事例を「見直し・心がけ」「省エネ技術」の視点からご紹介します。
目次
-
工場における省エネルギーの必要性と対策
-
工場における省エネ対策事例【見直し・心がけ編】
-
工場における省エネ対策事例【省エネ技術編】
-
まとめ:工場の省エネ対策で、環境負荷の軽減と生産性の向上を実現しよう!
1.工場における省エネルギーの必要性と対策
工場では多くのエネルギーを消費するため、各工場において省エネルギー対策が求められます。工場における省エネルギーの必要性や対策方法について解説します。
工場のエネルギー消費の現状
日本国内における製造業のエネルギー消費量は、世界金融危機や東日本大震災などの影響で2008年度以降減少傾向です。2021年度は新型コロナウィルスの影響からの経済回復で前年比4.8%増加しましたが、第一次石油危機が始まった1973年当時と比較すると、2021年度のエネルギー消費は約20%減少しています。その原因は、素材産業から加工組立型産業へのシフトに加え、省エネの進展が挙げられます。
出典:資源エネルギー庁「資源エネルギー庁「令和4年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2023)第2節 部門別エネルギー消費の動向」
工場における省エネルギーの意義
工場において省エネルギーには社会的な意義と、経済的な意義があります。社会的な意義とは、工場以外でも言えることですが、2050年までにカーボンニュートラル(地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出を、森林などによる吸収と差引してゼロにすること)の実現に、省エネが寄与することです。経済的な意義とは、省エネによるコストの削減や省エネのための工程見直しなどに伴う生産性の向上です。
出典:一般財団法人省エネルギーセンター「工場の省エネルギーガイドブック2023」」p1
工場の省エネ法規制
工場の省エネについては、「工場等に係る省エネ法」による規制も定められています。事業者全体のエネルギー使用量(原油換算値)が年間1,500kl以上であり、特定事業者又は特定連鎖化事業者に指定並びに認定管理統括事業者に認定された事業者には、省エネ措置の実施などの義務や、年平均1%以上のエネルギー消費原単位低減などの目標が課せられます。さらに工場単位のエネルギー使用量が原油換算で年間1,500kl以上の場合は「エネルギー管理指定工場」としてエネルギー管理者の選任、行政への定期報告等が義務化され、行政から必要に応じて指導・助言、報告徴収・立入検査、合理化計画の作成指示などが行われます。定期報告書は事業者全体及びエネルギー管理指定工場等のエネルギー使用量等の情報を記載し提出が必要です。
出典:資源エネルギー庁「工場・事業場の省エネ法規制 事業者の区分と義務」
出典:資源エネルギー庁「工場・事業者の省エネ法規制 特定事業者向け情報」
出典:資源エネルギー庁「工場・事業所の省エネ法規制 定期報告書・中長期計画書」
工場における省エネルギー管理
工場での省エネルギー管理には、以下のような取り組みが求められます。
・管理体制:トップの意思表示・担当者任命・人材育成など
・エネルギー可視化:データの共有・理解・分析など
・計測・記録:エネルギー使用量・設備運転状況など
・保守管理:保守管理基準・補修・更新計画など
・運転管理:運転マニュアルの作成・見直しなど
こうした項目を着実に実施し、省エネにつなげていくことが重要です。
出典:一般財団法人省エネルギーセンター「工場の省エネルギーガイドブック2023」」p2
工場での省エネルギーチェック
一般財団法人省エネルギーセンターでは、「工場の省エネルギーチェック項目」を公表しています。チェック項目ごとに取り組みレベルが示されており、段階を踏んだ対策を検討する参考になります。
取り組みレベル
1:日常業務に組み込んで実施できるもの
2:専門家のアドバイス等により自らが実施できる取り組み
3:設備投資が必要な取り組み
省エネ対策の第一歩としては、レベル1から着手するのがよいでしょう。レベル1のチェック項目例としては「省エネ活動を継続的に行う仕組み(省エネ委員会など)があるか」「重点的に管理すべき省エネ対象設備を特定しているか」「月・年度毎のエネルギー使用量を集計しているか」などがあります。
出典:一般財団法人省エネルギーセンター「工場の省エネルギーガイドブック2023」」p3
2.工場における省エネ対策事例【見直し・心がけ編】
工場の省エネ対策においては、身近な業務の見直しや普段からの心がけが重要です。実際の対策事例をご紹介します。
宮城ニコンプレシジョン株式会社
宮城ニコンプレシジョン株式会社では、24時間稼働していた循環ポンプについて、生産をしていない期間、休日の24時間、凍結の心配がない4~11月の夜間15時間(17:30~翌日8:30)については停止することとした結果、年間4.7klの省エネと33.2万円のコスト削減になりました。またコンプレッサの吐出圧を0.68MPaから0.6MPaへと下げることによって、年間2.3klの省エネと15.9万円のコスト削減が実現しました。
出典:一般財団法人省エネルギーセンター「省エネ取組事例紹介」p11-12(2022/2/16)
太子食品工業株式会社
太子食品工業株式会社では、4台稼働していたボイラーを2台へ集約したことで運転効率が年間154.8kl向上し、重油使用料年間693.5万円の削減につながりました。また空気配管からの圧縮空気漏れを点検することによる年間8.6klの省エネおよび電力使用料年間54.4万円の削減や、蒸気配管からの蒸気漏れを補修することによる年間2.5klの省エネおよび11.4万円のコスト削減も実現しています。
さらに冷蔵用冷凍機の温度設定最適化による年間6.3klの省エネと電力使用料39.8万円の削減、空調を使用しない期間に空調の電源ブレーカーを遮断することによる待機電力の削減(年間の省エネ効果0.5kl、コスト▲3万円)など、地道な省エネ対策を多数実施しています。
出典:一般財団法人省エネルギーセンター「省エネ取組事例紹介」p15-16(2022/2/16)
3.工場における省エネ対策事例【省エネ技術編】
工場では、設備投資による省エネ対策も有効です。省エネ技術による工場の省エネ事例をご紹介します。
TOTO株式会社
TOTO株式会社では、環境に配慮した「グリーンファクトリー」のモデル工場として、滋賀工場 新西棟を2012年に建設しました。排熱を回収して再利用する省エネ型高効率焼成窯(従来型の窯対比で約71%の省エネ効果)、負荷状況に合わせて空調を個別制御する省エネ型新空調設備(従来対比で29%のCO2削減)、屋根や外壁の高断熱化、棚卸負荷を軽減し生産性を向上させる個体識別バーコード管理など、随所に省エネ技術が応用されています。工場全体では電力量18%、都市ガス使用量48%の削減を実現しています。
レンゴー株式会社
段ボール製造業のレンゴー株式会社は、金津工場(福井県)にて、設備の能力強化による製品の乾燥効率アップや、断紙モニタリングシステムや回転体振動監視システム、ボイラ異常予兆検知システムを開発・導入したことにより、2022年度に2018年度対比で10.7%に相当する年間6,950klの省エネを実現しました。
出典:レンゴー株式会社「金津工場が『省エネ大賞』資源エネルギー庁長官賞を受賞しました」(2024/2/7)
株式会社豊田自動織機
株式会社豊田自動織機は安城工場(愛知県)において、製品の静電気による破壊を防止するために、全館空調による湿度対策を実施していました。そこで必要なエリアのみに蒸気によらず除電が可能なイオナイザーや空間除電装置を導入し、工場全体の室同管理を緩和した結果、LNG使用量を原油換算で年間160kl(約40%)削減することに成功しました。
出典:株式会社資生堂「資生堂 掛川工場の取り組みが 「2022年度省エネ大賞」の「資源エネルギー庁長官賞」を受賞」(2022/12/22)
4.まとめ:工場の省エネ対策で、環境負荷の軽減と生産性の向上を実現しよう!
工場は大量のエネルギーを必要とする施設であり、法律上も省エネ対策が求められています。工場でできる省エネ対策は、日常の心がけから大規模な設備投資まで幅広い方法が考えられますので、工場の省エネ対策を検討する企業では、できることから着手して徐々にステップアップしていくとよいでしょう。
工場の省エネ対策を徹底して、環境負荷の軽減と生産性の向上を同時に実現することを目指しましょう。