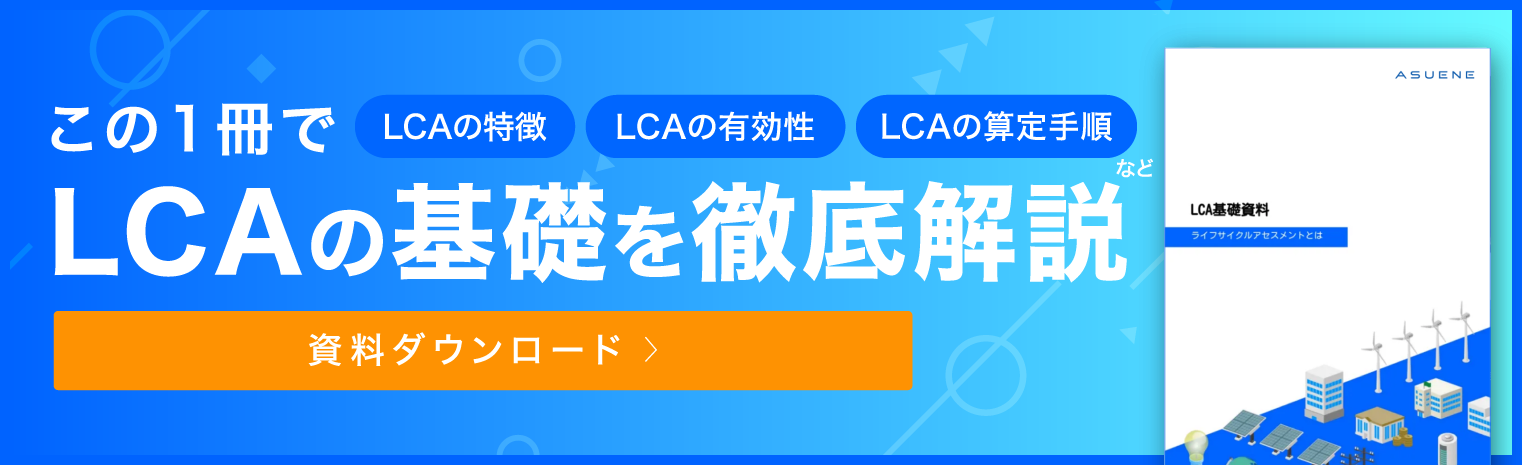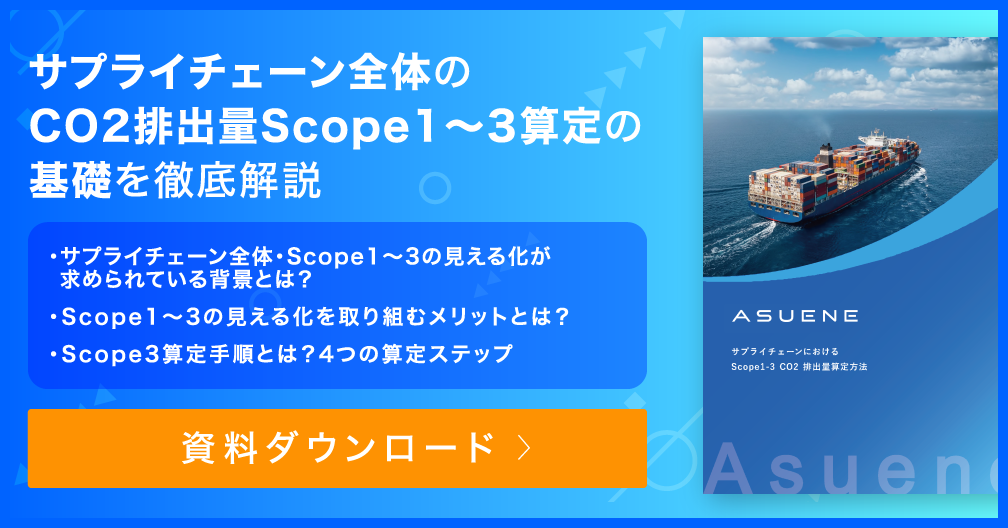J-クレジットとは?種類や活用事例などを解説
- 2024年05月22日
- CO2削減
J-クレジットとはどのようなものか、種類や具体例についてわかりやすく解説します。地球温暖化の原因となる温室効果ガス を削減するためには、温室効果ガスの排出量を減らすと同時に、森林などによるCO2の吸収量増加も重要な取り組みとなります。J-クレジットは、日本における温室効果ガスの排出削減やCO2吸収量増加につながるさまざまな事業を支援する取り組みで、複数の省庁を横断して運営されています。
本記事ではJ-クレジットの概要や種類、実際の活用事例などについて取り上げます。
目次
-
J-クレジットとは
-
J-クレジットの種類
-
J-クレジット活用事例
-
まとめ:色々な種類のJ-クレジットを活用して、カーボンオフセットしつつ環境対策を支援しよう!
1. J-クレジットとは
J-クレジットは、その創出者と購入者双方にメリットのある制度です。J-クレジットの概要について解説します。
J-クレジットとは
J-クレジットとは、経済産業省・環境省・農林水産省が運営する、温室効果ガスの排出削減・吸収量をクレジットとして認証する制度です。クレジットと言っても資金の借り入れや代金後払いを意味するものではなく、「創出者」が省エネ・再エネ設備の導入によって削減した温室効果ガスの排出量や森林管理によって増加させたCO2の吸収量を指します。
この排出削減量などを国が「J-クレジット」として認証し、企業などが購入できるようにシステムを構築しています。J-クレジットを購入した企業は、自らが排出した温室効果ガスの対外公表や報告にあたって、購入したJ-クレジット分を差し引いて排出量を算出することができます(カーボン・オフセット)。
出典:J-クレジット「J-クレジット制度について」p3-5(2023/11)
J-クレジット制度の目的
J-クレジットは2013年に、前身となるJ-VER制度と国内クレジット制度を一本化してして誕生しました。J-クレジット制度は、自治体や中小企業による温室効果ガスの削減または吸収量の増加につながる事業や、クレジットの活用による国内での資金循環を促すことを目的としています。日本政府の「地球温暖化対策計画」においては、J-クレジット制度を分野横断的な施策、カーボン・オフセットの推進を「脱炭素型ライフスタイルへの転換」と位置づけています。
出典:J-クレジット「J-クレジット制度について」p3,9(2023/11)
J-クレジットのメリット
J-クレジットの購入者には、以下のようなメリットがあります。
-
対外的な温室効果ガス排出量の報告・公表時に、J-クレジット購入分を差し引くことができる。
-
自組織の温室効果ガス削減目標の達成につながる。
-
創出者への資金提供によって、社会貢献になる。
またJ-クレジットの創出者にも、以下のようなメリットが生じます。
-
クレジット売却益を得ることができる。
-
地球温暖化対策への貢献になる。
-
J-クレジット制度に関わる企業や自治体との関係強化になる。
ただし、クレジット創出者はJ-クレジットによって売却した削減量は、自組織の削減量としては算入できなくなる点には注意が必要です。
出典:J-クレジット「J-クレジット制度について」p4(2023/11)
J-クレジットの登録、認証、市場動向
J-クレジットの認証を受けるためには、まずプロジェクトを計画し、登録審査の承認を得る必要があります。その後プロジェクトを実施した後、実現した削減量についてクレジットとしての認証が与えられます。J-クレジットのプロジェクト登録や認証の件数は、以下の通り制度発足以来大きく伸びています。
|
2013年(制度発足年) |
2023年9月15日時点 |
|
|
プロジェクト登録件数 |
244件 |
1,022件 |
|
クレジット認証量 |
3万t-CO2 |
905万t-CO2 |
J-クレジットは2016年より入札販売が行われていますが、以下の通り再エネ発電由来のクレジットの販売量の割合が特に大きく、平均落札価格も上がっています。
入札開催時期 |
再エネ発電 |
省エネ他 |
||
|
販売量 |
平均落札価格 |
販売量 |
平均落札価格 |
|
|
2023年5月 |
259,721t |
3,246円/t |
41,410t |
1,551円/t |
|
2018年1月* |
400,000t |
1,716円/t |
100,000t |
1,148円/t |
*再エネ発電を省エネ他と分けて販売するようになった最初の入札
平均落札価格の上昇は、J-クレジットに対する需要の高まりを示しています。
出典:J-クレジット「J-クレジット制度について」p6(2023/11)
出典:J-クレジット「制度概要およびクレジット創出概要」p52-53,55,57(2023/11/20)
2. J-クレジットの種類
J-クレジットは「方法論」などによって区分されています。J-クレジットの種類について解説します。
J-クレジットの方法論の種類
J-クレジットの「方法論」とは、温室効果ガスを削減する技術や方法ごとに排出削減量の算定方法やその検証方法などを規定したものです。2023年11月時点では分類別に以下の承認状況となっています。
|
分類 |
承認数 |
具体例 |
|
省エネルギー等 |
42 |
ボイラー・空調設備・照明設備などの導入 |
|
再生可能エネルギー |
11 |
太陽光発電・水力発電・風力発電などの導入 |
|
工業プロセス |
5 |
マグネシウム溶解鋳造用カバーガスの変更 |
|
農業 |
6 |
家畜排せつ物管理方法変更・バイオ炭農地施用 |
|
廃棄物 |
3 |
バイオ潤滑油の使用 |
|
森林 |
3 |
森林経営活動・植林活動・再造林活動 |
このように、J-クレジットには7つの分類と、合計70の方法論があります。
出典:J-クレジット「J-クレジット制度について」p14-17(2023/11)
J-クレジットのプロジェクトの形態の種類
J-クレジットは、プロジェクトの形態によって「通常型」と「プログラム型」に分かれます。通常型は、原則として1つの工場・事業所等における削減活動を1つのプロジェクトとして登録する形態です。これに対しプログラム型は、複数の削減・吸収活動を取りまとめ1つのプロジェクトとして登録する形態です。
たとえば家庭の屋根への太陽光発電設備導入では、個々の家庭がJ-クレジットの創出者になることは困難ですが、発電設備の施工会社や太陽光発電へ補助金を交付する自治体などが、取りまとめ事業者としてプログラム型のJ-クレジットを申請することができます。
出典:J-クレジット「J-クレジット制度について」p13(2023/11)
出典:環境省「J-クレジット制度の概要と最新の動向」p9(2024/2/7)
3. J-クレジット活用事例
J-クレジットによって、さまざまな取り組みが進んでいます。J-クレジットの活用事例をご紹介します。
ナカバヤシ株式会社
アルバム・製本・事務機器製造などを手がけるナカバヤシ株式会社(以下「ナカバヤシグループ」)は、2022年に株式会社田部(以下「田部グループ」)が販売するオフセット・クレジット(J-VER)1,800t-CO2を購入しました。J-VERはJ-クレジットの前身となる制度で、2022年にJ-クレジットへの移行が完了しています。田部グループは森林の間伐整備によってCO2吸収量を増大させつつ、化石燃料を森林の間伐から生まれた自然バイオマスに転換する取り組みによってクレジットを創出しています。
ナカバヤシグループは島根県で5つの工場を稼働しており、地域課題解決へ貢献することを企図して、島根県で森林管理に注力している田部グループのJ-クレジット購入によって、CO2吸収の取り組みを支援しています。
出典:ナカバヤシ株式会社「オフセット・クレジット(J-VER)の活用」
農林中央金庫
農林中央金庫は全国森林組合連合会と連携して、J-クレジットの中でも「森林」分野のクレジット創出を支援するプラットフォーム(システム基盤)を、2023年に立ち上げました。森林由来のJ-クレジットは、森林所有者の合意や販売先開拓が難航するなどの理由で、取組みが十分に進まない状況にありました。クレジットの組成から販売に至る一 連の取組みをサポートするプラットフォームが構築されたことによって、森林や林業に民間資金が流入し、持続的な森林管理が推進されることが期待されます。
出典:農林中央金庫「森林由来クレジットによるカーボンニュートラル社会への貢献を目指した連携協定の締結とプラットフォームの立上げについて」(2023/1/13)
東海ガス株式会社
東海ガス株式会社は、静岡県藤枝市・しずおかフィナンシャルグループと協力し、「藤枝型森林カーボンクレジット」のスキームを構築しました。藤枝市の豊富な森林資源に関して、J-クレジットの利用と森林資源の有効活用を促進することが目的です。
取り組みの第一弾として、藤枝市内の2社(渡辺林業株式会社・TMホーム株式会社)の所有する森林によるCO2吸収量について、J-クレジットのプロジェクト登録を行いました。今後年間700万t-CO2のクレジット創出が見込まれます。
出典:東海ガス株式会社「官民連携で『藤枝型森林カーボンクレジット』を展開~地域におけるJクレジット創出と木材の流通の循環モデル確立~」(2024/3/12)
4. まとめ:色々な種類のJ-クレジットを活用して、カーボンオフセットしつつ環境対策を支援しよう!
カーボンオフセットの手段となるJ-クレジットは、再生可能エネルギーを中心にクレジットの創出や利用が拡大しています。J-クレジットは単にカーボンオフセットの手段であるというだけでなく、クレジット創出者の環境保全対策を支援することにもつながります。J-クレジットの活用によって革新的な取り組みへの資金供給が進めば、日本の環境課題解決も進むでしょう。
色々な分野やプロジェクト形態のJ-クレジットを活用して、自社の温室効果ガス排出量をオフセットしつつ、環境対策を支援しましょう。