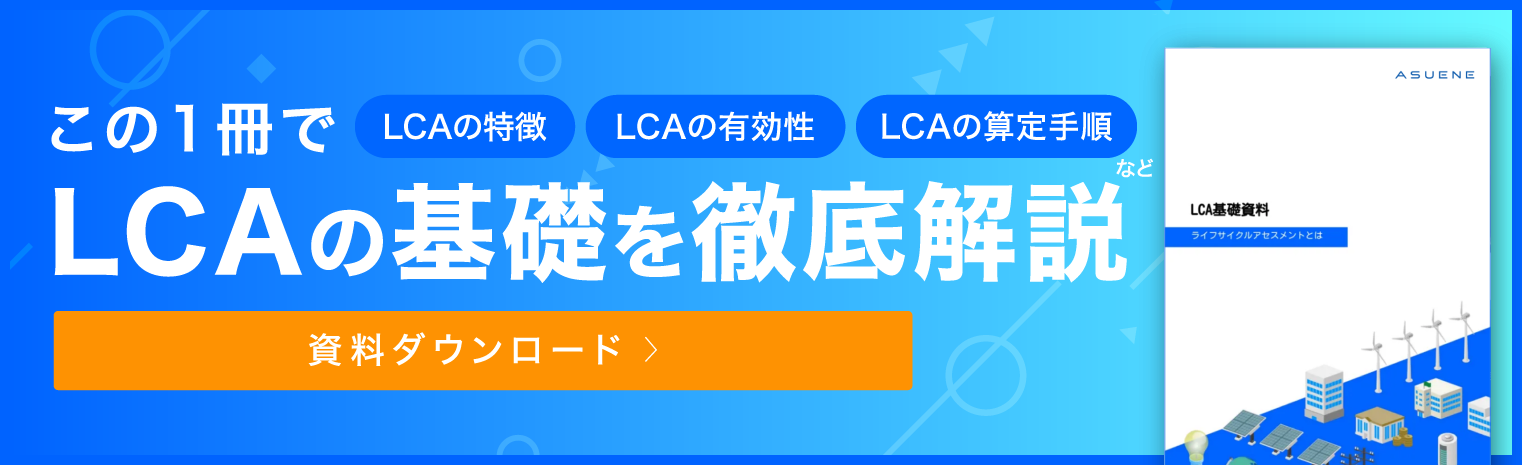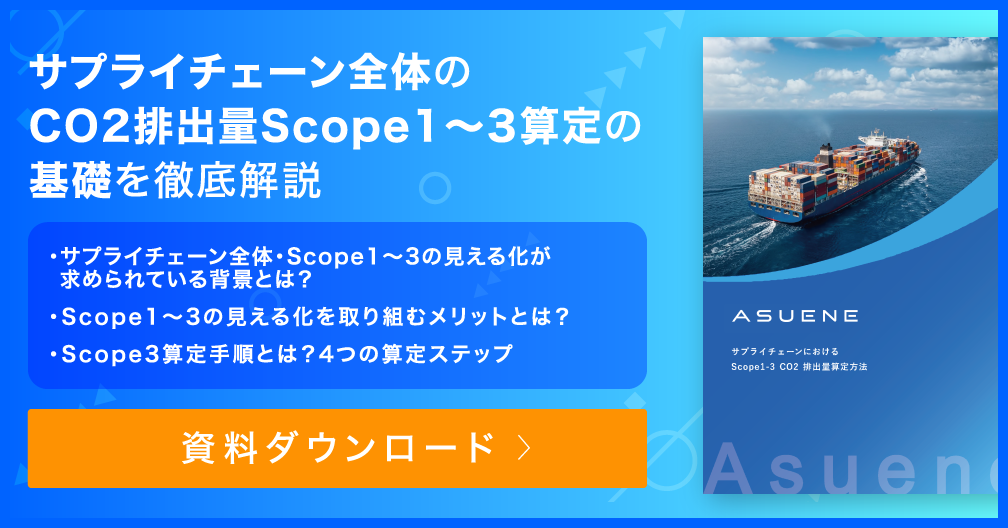【2024年度版】日本の再生可能エネルギー由来電力の割合は?
- 2024年01月31日
- 発電・エネルギー

日本では、2030年度までに発電方法における再生可能エネルギーの割合を36〜38%にするという目標が掲げられており、再生可能エネルギーがますます普及していくことが予想されます。再生可能エネルギー由来電力の導入をご検討中の法人の皆さまは、国内外の動向を知った上でどのように取り組むかを考えていただければと思います。この記事では、最新版となる日本における再生可能エネルギー由来電力の割合と今後の見通しを中心にご紹介します。
目次
-
日本/世界で再生可能エネルギー導入が求められる背景
-
日本のエネルギー事情
-
日本における再生可能エネルギー普及の見通し
-
世界各国の再生可能エネルギーに関する取り組み
-
まとめ:国内外の再生可能エネルギーによる電力の普及状況を理解し、今後の導入につなげよう!
1. 日本/世界で再生可能エネルギー導入が求められる背景
再生可能エネルギーという言葉が、最近ニュースなどでもよく取り上げられるようになりました。ここでは日本を含めて世界各国で再生可能エネルギーの導入が求められるようになった3つの背景をご紹介します。
地球温暖化による異常気象
近年、世界各国で問題視されているのが、地球温暖化による異常気象です。地球温暖化の主な原因であるCO2の排出量を削減しようとする試みが、再生可能エネルギーへの注目につながっています。
再生可能エネルギーが注目されている理由は、再生可能エネルギーが発電時にほとんどCO2を排出しないためです。発電設備の建設や廃棄などを含めたライフサイクル全体で考えても、化石燃料発電と比較するとCO2排出量を大幅に削減することができます。
たとえば石炭火力の発電によるライフサイクルCO2排出量が943g-CO2/kWhであるのに対し、太陽光の同排出量は38g-CO2/kWhです。このように化石燃料による発電と比較して大幅にCO2排出量を削減できることが、再生可能エネルギーが注目されている背景にあります。

出典:環境省『1.再生可能エネルギー導入加速化の必要性など』(p2)
国内でのエネルギー自給率の低さ
国内でのエネルギー自給率の低さも、再生可能エネルギーが注目されている背景にあります。経済産業省の発表によると、日本は1960年には石炭や水力など国内の天然資源によるエネルギー自給率が58.1%もありました。しかしエネルギー消費の増加によって、1970年には15.3%に大幅にダウンし、その後もわずかに増減を繰り返しながらも低い水準のまま保たれ、2021年度のエネルギー自給率は13.1%です。
出典:資源エネルギー庁『令和4年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2023)』
パリ協定の採択
日本を含めた世界各国で、再生可能エネルギーの導入が進んでいます。世界が歩みを揃えた背景には、パリ協定の採択があります。パリ協定は、2015年にフランスで採択された、2020年度以降の気候変動抑制に関する国際的な枠組みです。パリ協定では「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」という世界共通の目標が掲げられ、新興国や途上国も含む全ての主要排出国が地球温暖化対策に取り組むこととなりました。
出典:資源エネルギー庁『今さら聞けない「パリ協定」 ~何が決まったのか?私たちは何をすべきか?~』(2017/8/17)
2. 日本のエネルギー事情
日本は今後、2030年度までに再生可能エネルギーの割合を36〜38%程度とすることを目標としています。ここでは、現在の日本におけるエネルギー事情をご紹介します。
日本のエネルギーに占める化石燃料の割合
経済産業省の「エネルギー白書2023」によると、2020年度の日本のエネルギーに占める化石燃料の割合は88.9%と高い水準にあります(内訳は石油38.4%、石炭26.5%、天然ガス24.0%)。日本は化石燃料のほとんどを輸入に頼っているため、安定的なエネルギーの供給が大きな課題です。

出典:資源エネルギー庁『令和4年度エネルギーに関する年次報告 (エネルギー白書2023)』
日本における再生可能エネルギーによる発電割合
2020年度日本の再生可能エネルギー電力比率は約19.8%となっています。これは主要国対比で見た場合、相対的に低い水準です。たとえばカナダでは再生可能エネルギー電力比率が67.9%となっていますし、欧米に比べ同比率が低い中国でも27.7%です。
日本も再生可能エネルギーによる発電設備容量は世界第6位、太陽光発電導入容量は世界第3位となっているのですが、国内電力需要に対して再生可能エネルギーによる発電量が追いついていません。日本が2030年度までの目標とする、再生可能エネルギーによる発電割合を36〜38%にするためには、さらなる再生可能エネルギー導入の推進が求められます。

出典:資源エネルギー庁『令和4年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2023)』
出典:資源エネルギー庁『エネルギーの今を知る10の質問』(2023/02)
3. 日本における再生可能エネルギー普及の見通し
2050年までの脱炭素社会を実現するために、日本は再生可能エネルギーを最大限に活用していく方針となっています。ここでは再生可能エネルギーの導入に関して、日本が掲げる目標と今後の普及の見通し、現在日本が実施している取り組みの事例をご紹介します。
日本が掲げる目標
2022年4月に資源エネルギー庁が発行した「今後の再生可能エネルギー政策について」では、エネルギーミックス改定において、2030年度の温室効果ガス46%削減に向けた野心的目標として、電源構成比の36〜38%を再生可能エネルギーとすることが発表されました。内訳は、太陽光発電が14〜16%程度、風力発電が5%程度、水力発電が11%程度、地熱発電が1%程度、バイオマスが5%程度になっています。
その他の電源構成については、原子力の割合を20〜22%、石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料の割合を41%にする方針です。

出典:資源エネルギー庁『今後の再生可能エネルギー政策について』p5(2022/4/7)
日本における再生可能エネルギー普及の見通し
2023年2月10日に、「GX実現に向けた基本方針」が閣議決定されました。ここでは、エネルギーの安定供給や脱炭素分野で新たな市場を生み出し、日本の経済成長につなげていく方針が示されています。さらに同年5月31日には、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(GX脱炭素電源法)」が成立しました。
このように再生可能エネルギーによる電源構成比を36〜38%にするという目標に向けた取り組みは加速しており、再生可能エネルギーの普及が拡大することが期待されます。
出典:経済産業省『今後の再生可能エネルギー政策について』p1(2023/6/21)
再生可能エネルギー普及のための制度:FIT、FIP
日本では2012年に固定価格買取(FIT)制度が施行されました。FIT制度は、再生可能エネルギーの普及を目的とし、太陽光発電や風力、水力、地熱、バイオマスを対象とし発電したエネルギーを電気事業者が国が定める料金で一定期間買い取るというものです。安定した利益を得ることができるため、日本では発電事業が急増しました。FIT制度が施行される前は約5GWだった太陽光発電の累積導入量が、2022年度には約85GWにまで伸びています。
また、2022年4月より電力市場価格に補助金(プレミアム金)が上乗せされた金額が支払われるFIP制度が始まったことからも、国が再生可能エネルギーの普及に力を入れていることがわかります。
出典:環境エネルギー政策研究所『国内の2022年度の自然エネルギー電力の割合と導入状況(速報)』(2023/9/5)
4. 世界各国の再生可能エネルギーに関する取り組み
経済産業省によると、世界全体の再生可能エネルギー発電設備の容量は、2015年には2000GW程度で、2020年には3000GW程度まで達しています。ここでは、アメリカと欧州の目標と取り組み事例をご紹介します。
出典:資源エネルギー庁『国内外の再生可能エネルギーの現状と 今年度の調達価格等算定委員会の論点案』p3(2022/10)
アメリカの目標と取り組み事例
2021年時点のアメリカの再生可能エネルギーの発電量は全体の21%を占めており、中国に次いで第2位でした。バイデン大統領は、気候変動及び再生可能エネルギーに意欲的であり、2022年に約54兆円規模の気候変動対策が含まれたインフレ抑制法(IRA)を可決しています。また、新たに環境対策に取り組む企業への税控除措置が盛り込まれたクリーンエネルギー技術促進を新設するなど、積極的に環境問題に取り組んでいます。
出典:新電力ネット『中間選挙終えたアメリカ、気候変動対策やエネルギー政策の行方は?』(2022/11/29)
EUの目標と取り組み事例
EUは、気候変動問題や再生可能エネルギー導入へ積極的に取り組み、環境対策で世界を牽引しています。とくに2022年は、天然ガス最大の輸入国であったロシアのウクライナへの軍事侵攻もあり、天然ガス脱却へ勢いが増しています。ここでは、ドイツとデンマークの現状や目標、取り組みなどをご紹介します。
出典:EU MAG『EU、COP28で世界の気候野心の引き上げ追求』
(1)ドイツ
ドイツは、2000年時点で7%だった再生可能エネルギーの電源構成比率が2020年には45%に達しています。2022年はロシアのウクライナ軍事侵攻もあり、これまで以上に天然ガス依存からの脱却に取り組んでいます。実際に、2022年の新たな再生可能エネルギー法(EEG法案)を可決して、2030年に80%以上、2035年には100%を目指すとしています。
出典:環境エネルギー政策研究所『2021年の自然エネルギー電力の割合』(2022/4/4)
(2)デンマーク
デンマークは、再生可能エネルギーを牽引している国の1つです。2030年までに再生可能エネルギーによる電力の割合を100%以上とすることを目指しており、2000年時点で17%と高い割合でしたが、2021時点ですでに74%に達しています。特に風力・太陽光の変動性自然エネルギー(VRE:Variable Renewable Energy、気象条件によって発電量が変動するエネルギー)で電力の50%以上を供給する体制が実現しています。
出典:環境エネルギー政策研究所『2021年の自然エネルギー電力の割合』(2022/4/4)
6. まとめ:国内外における再生可能エネルギーによる電力の普及状況を理解し、今後の導入につなげよう!
再生可能エネルギーによる電力の導入をご検討中の法人の皆さまが知っておくべき、国内外における再生可能エネルギー普及の現状や今後の見通しなどについてお伝えしました。
日本では再生可能エネルギーの電源構成比は主要各国に比べ低い水準ですが、環境対策・エネルギー自給率対策などを背景に、再生可能エネルギーの普及促進が社会課題となっています。国内外における再生可能エネルギーによる電力の普及状況を理解し導入を検討しましょう。