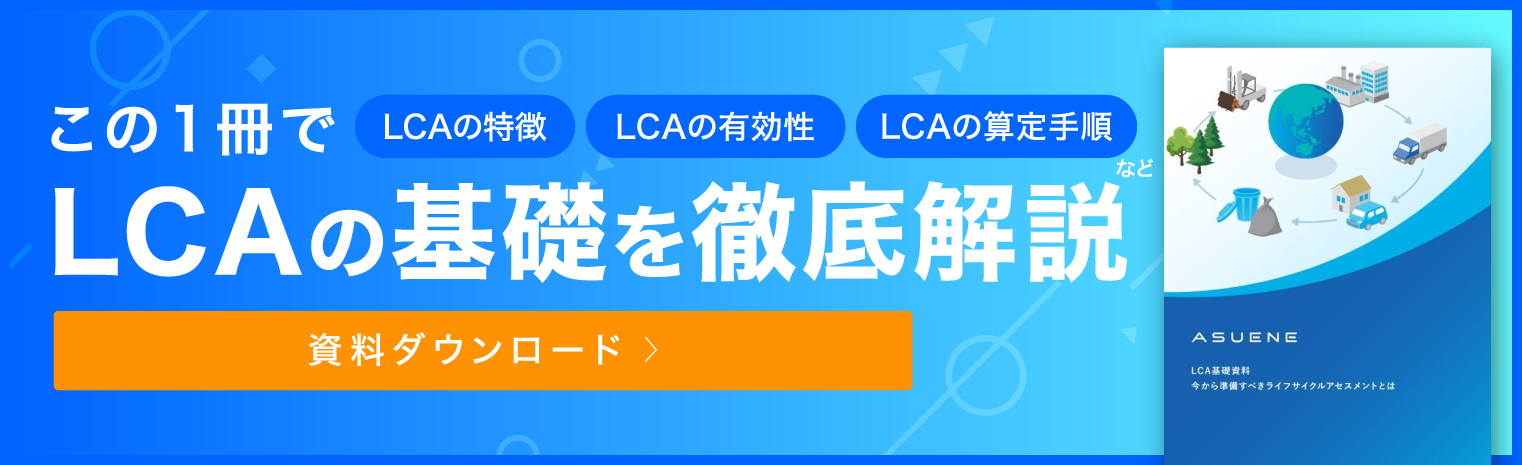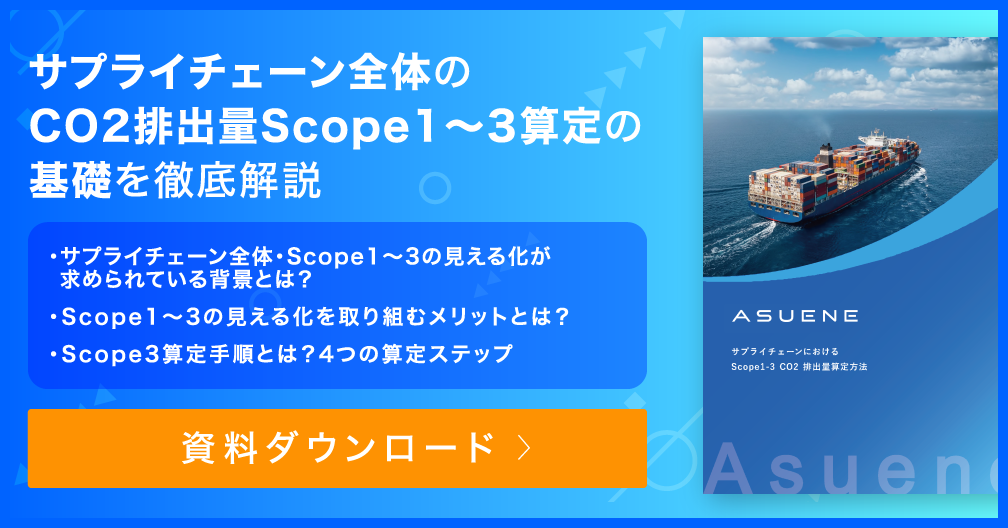日本の再生可能エネルギーの普及が遅れた理由と取り組み状況
- 2022年06月15日
- 発電・エネルギー

世界での導入が進んでいる再生可能エネルギーですが、日本では普及が進んでいません。日本で再生可能エネルギーの普及が遅れている理由とは何か、日本は遅れを取り戻すために具体的にどのようなことを行っているのでしょうか。
この記事では、再生可能エネルギーの導入を検討している法人の皆さまが、知っておくべき基本的な知識についてご紹介します。日本が現在置かれている状況について理解を深め、再生可能エネルギーの導入につなげていただければと思います。
目次
-
再生可能エネルギーが日本で遅れた理由・日本の状況
-
日本の再生可能エネルギーが遅れている3つの理由
-
再生可能エネルギーの遅れを取り戻すための日本の取り組み
-
日本の状況を理解し、再生可能エネルギーの導入につなげよう!
1. 再生可能エネルギーが日本で遅れた理由・日本の状況
日本で再生可能エネルギーの普及が遅れた理由を知る前に、現在の日本における再生可能エネルギーの導入状況に関する知識から深めていきましょう。ここでは、世界での導入状況についてもご紹介します。
日本の再生可能エネルギーの発電比率
経済産業省・資源エネルギー庁の発表によると、2019年度の日本の発電電力量に占める再生可能エネルギーの比率は18%です。他の主要国の導入状況と比較すると、日本の再生可能エネルギーの比率は低いです。

出典:資源エネルギー庁『日本のエネルギー 2020年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」』
日本の再生可能エネルギーの内訳を見ると、水力発電が7.7%で、水力発電以外が10.3%です。水力発電以外の再生可能エネルギーで最も多いのが太陽光発電で、太陽光発電の導入量は中国、アメリカに次ぐ第3位です。

出典:資源エネルギー庁『日本のエネルギー 2020年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」』
世界の再生可能エネルギーの発電比率
経済産業省・資源エネルギー庁の発表によると、2019年度の主要国の発電比率は以下のようになっています。
-
カナダ 66.3%
-
イタリア 39.7%
-
ドイツ 35.3%
-
スペイン 38.2%
-
イギリス 33.5%
-
中国 25.5%
-
アメリカ 16.8%
-
フランス 19.6%
このように主要国では、再生可能エネルギーの普及が進んでいるのですが、その原動力となっているのが風力発電と太陽光発電です。特に著しい伸びを見せているのが、イギリスの風力発電です。イギリスは洋上風力の大量導入により2010年にはわずか3%だった風力発電の比率を2020年に24%にまで伸ばしています。

出典:Global Wind Report 2014 を元にアスエネが作成
洋上風力とは、陸上ではなく海域に風力発電設備を設置するもので、海に囲まれた日本においても注目されています。
出典:東京新聞『再生エネルギー発電、日本が伸び悩む理由は?』(2021/3/9)
出典:資源エネルギー庁『新法施行後、「洋上風力発電」に向けた動きは今どうなっている?』(2019/12/25)
出典:資源エネルギー庁『日本のエネルギー2018 「エネルギーの今を知る10の質問」』
2. 日本の再生可能エネルギーが遅れている3つの理由
日本は太陽光発電の導入量は世界第3位ながら、全体的に見ると主要国の中で、再生可能エネルギーの普及が遅れています。ここでは、日本における再生可能エネルギーの普及を阻んでいる3つの理由をご紹介します。
発電コストが高い
日本では、太陽光発電の普及は進んでいるものの、政府はさらなる太陽光発電の普及を目指しています。現在普及が遅れている理由として、発電にかかるコストの高さがあげられます。
資源エネルギー庁は、日本と欧州における太陽光発電システムにかかる費用比較を公表しているのですが、日本は欧州と比べて、発電するコストが2倍ほど高いです。

※日欧の太陽光発電(非住宅)システム費用比較。出典:資源エネルギー庁『再エネのコストを考える』(2017/9/14)
発電コストの高さは、日本の国民の負担も大きくしています。
国民は、「再エネ賦課金」という形で毎月の電気料金の中で、発電した電気を電気業者が買い取る費用を負担しています。新電力ネットの発表では、標準家庭の1ヶ月あたりの再エネ賦課金の負担が、2012年度は66円だったのに対して、2021年度には1008円にまで増加しています。日本は発電コストと国民の負担を下げることで、再生可能エネルギーの普及を進めていく方針です。
出典:新電力ネット『再生可能エネルギー発電促進賦課金の推移』

出典:電気新聞「FIT総額、2030年に4.5兆円へ。電中研が推計」(2020.6.18)を元にアスエネが作成
設備を設置する初期コストが高い
資源エネルギー庁の発表によると、日本は海外と比較すると、太陽光パネルや風力発電機本体を購入する費用が約1.5倍高く、工事費も約1.5~2倍高いです。再生可能エネルギーを導入するためのコストの高さも、普及が遅れている理由の1つです。
出典:資源エネルギー庁『資源エネルギー庁がお答えします!~再エネについてよくある3つの質問』(2018/3/16)
他国との電力ネットワークが構築されていない
太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーのデメリットとして、気候や天気に左右され、発電できる電力量が不安定であることがあげられます。大規模な停電を起こさないためには、電気の需要と供給のバランスが大切です。
陸続きの国だと、隣国と電気を送電線で送り合い、電力量をコントロールすることができますが、島国である日本は、電気を他の国と送り合うことができません。このことも、日本で再生可能エネルギーの普及が遅れている理由の1つです。
出典:資源エネルギー庁『資源エネルギー庁がお答えします!~再エネについてよくある3つの質問』(2018/3/16)
3. 再生可能エネルギーの遅れを取り戻すための日本の取り組み
日本は、第一次オイルショックの翌年である1974年に策定した「サンシャイン(SS)計画」をきっかけに、再生可能エネルギー普及の取り組みを本格的に始めていますが、他の主要国と比較すると導入が遅れています。
サンシャイン計画とは、石油だけに依存しないエネルギーの長期的な安定供給の確保を目指して策定された計画です。ここでは、日本が再生可能エネルギーの遅れを取り戻すために行っている取り組みについてご紹介します。
出典:資源エネルギー庁『再生可能エネルギーの歴史と未来』(2018/2/1)
競争を高める法律の制定
日本は、2012年に固定価格買取制度(FIT法)を施行したことにより、再生可能エネルギーによる発電比率が、2019年度において18%にまで急増しています。また、21年5月時点の情報では、2030年度の再生可能エネルギーの導入水準を36~38%として検討していると報道されています。
日本は再生可能エネルギーの遅れを取り戻し、この水準に達するために再生可能エネルギーに競争原理を取り入れた法律を策定しています。
これまでのFIT法では、発電した電気は一定期間、一定の料金で買い取られていたため、企業は安定した収入を得ることができていました。
2022年4月から新たに、市場価格に一定のプレミアを上乗せするFIP法を施行し、競争原理を盛り込むことで、再生可能エネルギーの導入件数の増加を目指しています。

出典:資源エネルギー庁『「法制度」の観点から考える、電力のレジリエンス ⑤再エネの利用促進にむけた新たな制度とは?』(2020/10/8)
発電コストの引き下げ
日本は再生可能エネルギーの発電コストが高く、そのことが再生可能エネルギーの遅れにつながっています。そこで政府は、固定価格買取制度(FIT法)における買取価格を下げるための取り組みを行っています。具体的には、コストの低減化に成功している事業者を基準に買取価格を設定するトップランナー方式を採用し、入札制度の競争率を上げることでコストの引き下げを図っています。
出典:経済産業省『「再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会報告書(案)」に対する意見』
4. まとめ:日本の状況を理解し、再エネの導入につなげよう!
この記事では、再生可能エネルギーの導入をご検討中の法人の皆さまが知っておくべき、日本の再生可能エネルギー事情に関する基本的な知識をお伝えしました。現在、日本は主要国と比べて再生可能エネルギーの導入に遅れを取っています。その背景には、発電コストや初期コストの高さや日本の地理的条件などがあります。
しかしながら、日本は今、本格的な二酸化炭素排出量削減に向けて動いています。その有効な手段として注目されているのが再生可能エネルギーです。日本の現在の取り組みへの理解を深めて、再生可能エネルギーの導入につなげていただければと思います。