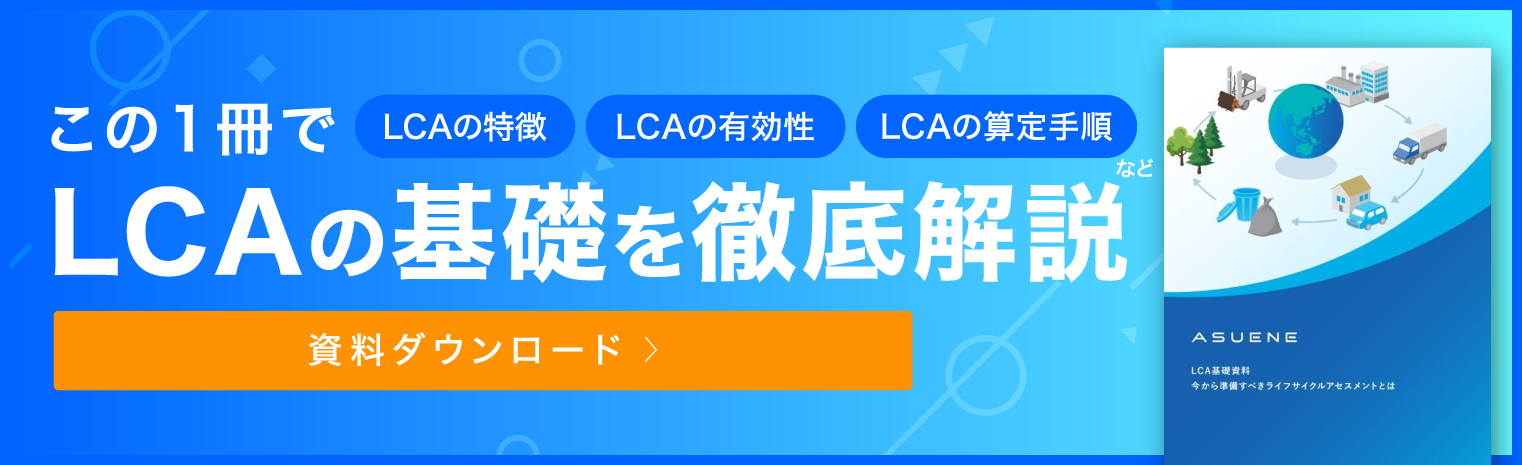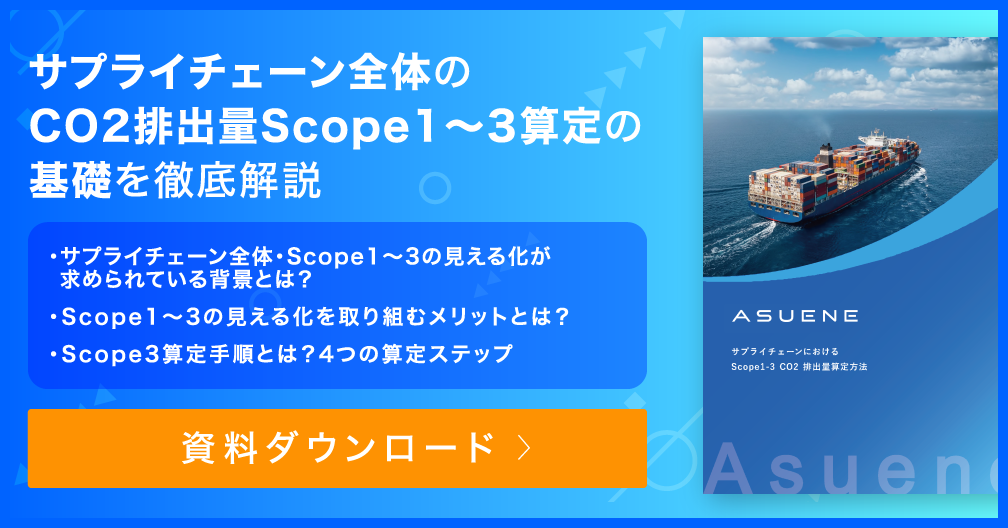スマートグリッドとは?企業の次世代の電力網について【徹底解説】
- 2022年06月15日
- 発電・エネルギー

「スマートグリッドとは?」
「スマートグリッドと従来の電力網は何が違うの?」
「スマートグリッドのメリットは?」
今回の記事ではこのような疑問を解決します。
スマートグリッドが開発された背景やメリット、スマートグリッドの仕組みや日本や海外での導入状況まで詳しく徹底解説していきます。
2~3分で読める記事ですので、是非最後まで読んでいってください!
目次
-
スマートグリッドとは?
-
スマートグリッドの背景とは?
-
スマートグリッドのメリットとは?
-
スマートグリッドの種類
-
まとめ
1. スマートグリッドとは?
結論から言うと、「無駄を省いたエコな送電網」です。別名「次世代送電網」「スマートコミュニティ」とも呼ばれるスマートグリッドですが、「結局今までの電力網と何が違うの?」と思った人もいるでしょう。一番の相違点は需要と供給の「両方」からコントロールできるところです。
従来の電力網では、「発電所→家庭・企業」という片一方の電力が供給されるだけでした。
しかし、スマートグリッドでは両方からコントロールをし、最適化しながら電力量を調整することができる電力網です。
つまりスマートグリッドは無駄な電力消費を減らすことができるという環境にやさしい送電網なのです。
上の図は、資源エネルギー庁が発表しているスマートコミュニティのイメージです。CEMS、BEMS、HEMSなど見慣れない横文字が並んでいますが、こちらについては後でご説明します。これらは、建物内のエネルギー量を管理するシステムだと思ってください。これらのシステムにより需給が制御されるのがスマートグリッドなのです。
2. スマートグリッドの背景とは?
まず、アメリカでの安定的な電力供給の需要の高まりに伴い開発され、次にヨーロッパで再生可能エネルギーの大量導入の必要性が高まり大きく浸透した、というのが大まかな背景です。
スマートグリッドが普及していなかった当時の アメリカでは、送電網の設備への投資が適切に行われていませんでした。それがきっかけで設備が老朽化し、電力供給に対する国民からの信頼度も低下しているという状況でした。
そのため、エネルギー省から次世代電力系統のビジョンを確立した「Grid 2030」※1が2003年に発表されました。この報告書に現在のスマートグリッドを定義づける文言が掲載されたことで、「スマートグリッド」が浸透します。
さらに2007年に発表された「エネルギー自立・安全保障法」により、スマートグリッドの技術実証予算措置が実施され、IEEE(アイ・トリプルイー:世界最大規模の電気・情報工学分野の技術標準化機関)※2による標準化が大きく実現することになりました。このようにしてスマートグリッドはアメリカにて開発が進んでいったのです。
アメリカにおけるスマートグリッドの進展
ヨーロッパでも、送電において国家間の連携が複雑化するなど電力問題を抱えており、アメリカで定義された「スマートグリッド」が浸透しました。また、風力発電などの再生可能エネルギーを大量導入するという目標も立てていました。「再生可能エネルギーを導入する」という目的によるスマートグリッドの開発は、ヨーロッパが先駆けとなりました。
それ以降、システムの安定運用が課題として明確になり、需要と供給のバランスを監視・制御する情報通信技術(ICT)の活用も進みました。
※1 出典:RedEléctricadeEspaña『Grid2030 Program』
※2 出典:IEEE 1888-2011『Standard for Ubiquitous Green Community Control Network』
3. スマートグリッドのメリットとは?
効率よく電力を供給できる
前述のように、スマートグリッドでは従来の電力供給と異なり、電力の需要量と供給量を正確に把握し、両方からコントロールすることができます。つまり、電力会社から「電力を増やして」「電力を抑えて」などの指示を送ることができるのです。
例えば、電力消費が少なくなった家庭があったとします。消費状況のデータを確認した電力会社は、従来よりも少ない発電量で済むことを把握することができます。もし他に電力消費が増えている家庭や企業があれば、抑えた電力の供給をそちらに回すことができます。
「効率的な電力供給」というメリットはさらに別のメリットにも派生します。
それは停電対策になることです。もしある地域で停電が起こったとしても、復旧の前にどこで停電が起こっているかを把握する必要があります。しかしスマートグリッドでは、電力量をネットワークを介して地域別に把握することができます。そのため、停電が起こったとしても、すぐに停電箇所を認知して、復旧させることができるのです。
効率よく再生可能エネルギーを導入できる
ざっくり言うなら、「大型発電所から電気を引っ張るだけだと心もとない、、、だから、各地域ごとに再生可能エネルギーを生み出す小型発電所を建てることで、その地域ごとに電力を地産地消しよう!」というようなこともできてしまうのです。
「どうして大型発電所からの電気に頼るのはダメなの?」という疑問を抱いている人もいるかと思います。結論から言うと、大型発電所からの電力供給が、長距離であることに問題があります。実は電気が私たちのもとに届くまでは、様々な工程を経て供給されています。まず、大型発電所が高電圧な電力を送電します。しかし電気の規模は家庭や企業などでそれぞれ違うかつ、無駄な電力ロスや送電に関するエネルギーの無駄を省くために、たくさんの変電所を経由して、少しずつ電圧を下げていく必要があります。その変電所を介する工程が多くなるほど、設備費などの配電にまつわるコストが増えていきます。
そこで比較的近場の各地域に、小規模な再生可能エネルギーの発電所を建設することによって、以上のような問題を解決できるのです。このような小規模のエネルギーネットワークのことをマイクログリッドといい、スマートグリッドの派生的なシステムとして期待されています。
出典:経済産業省北海道経済産業局「しえかん広報(資源環境エネルギー広報)」(令和元年10月号)
スマートグリッドの種類
スマートグリッドでは、スマートメーター(CEMS)を使ってエネルギーの最適化を行います。スマートメーターとは、通信機能のある電気メーターのことです。スマートグリッドが普及したスマートコミュニティは様々なシステムから構築されています。CEMSは、以下の4種類に分けることができます。
スマートメーターの種類
HEMS(ヘムス)
家庭内のエネルギー管理システムのことを指します。エネルギーの最適化に役立つ機能を持っています。電気・水道・ガスの消費量を確認でき、自宅に設置している太陽光パネルの発電量を把握できたり、照明機器やエアコンなどの家電製品の操作もすることができます。
BEMS(ベムス)
ビル内のエネルギー管理システムのことを指します。ビル内の設備などの管理を可視化して運転をコントロールすることで、エネルギー消費量を減らすことができます。
FEMS(フェムス)
工場内のエネルギー管理システムのことを指します。BEMSとシステムは同じで、工場内の設備や製造ラインなどのエネルギー消費量を可視化・最適化します。
MEMS(メムス)
マンション内のエネルギー管理システムのことを指します。マンション内の電力消費量をスマートメーターで計測・可視化し、空調や照明設備をコントロールすることで電力消費量を制御します。MEMSは家庭内のHEMSとビル内のBEMSの両方の機能を兼ね備えています。専有部での制御はHEMSに近く、共有部の制御はBEMSに近いです。
4. スマートグリッドの欧米と日本の状況
アメリカ
前述のように、アメリカでは大きな停電問題を抱えています。どれくらい深刻なのかというと、日本では平均停電時間が年間で225分なのに対し、アメリカ(ニューヨーク州)では409分※3です(2019年度の場合)。州によってばらつきがあるものの、まだまだ改善途中です。
主要国の年間停電時間の推移
出典:資源エネルギー庁「グラフで見る世界のエネルギーと『3E+S』安定供給③ ~国によってこんなに違う『停電時間』」(2019.7.18)
※日本が一時的に高くなっているのは、東日本大震災の影響。オバマ政権時にスマートグリッドに110億ドルを投資すると宣言していました。(2009年アメリカ復興・再投資法)※4大規模な電力網の整備で、安定性・信頼性を向上させるだけでなく、効率的な配送電による省エネや、再生可能エネルギーの大量導入などを図りました。しかしオバマ大統領の政権交代もあり、スマートグリッドの普及はまだまだ発展途上のままです。
※3 出典:東京電力ホールディングス『停電時間の国際比較』
※4 出典:IEEI『オバマ政権の環境・エネルギー政策(その4)』
ヨーロッパ
ヨーロッパは積極的に再生可能エネルギーの導入に力を入れていて、2019年には自然エネルギーは約34%、特に風力発電や太陽光発電なども約18%の導入率を達成しています。※5 しかし再生可能エネルギーによる電力供給は非常に不安定です。エネルギーを輸入せず、かつ二酸化炭素の排出量の少ない発電を目指すのであれば、電力供給を最適化できるスマートグリッドの普及が必要不可欠です。
さらに、ヨーロッパでは電力供給の最適化だけでなく、IoTによる生活インフラを普及させることで、環境に配慮しながら経済を発展させるという目標があります。そのためにはスマートグリッドの推進をし「スマートシティ」を構築する必要があります。ですから、他の先進国に比べてヨーロッパは比較的スマートグリッドの導入に積極的な地域です。
※5 出典:isep 環境エネルギー政策研究所『2019年(暦年)の自然エネルギー電力の割合(速報)』
日本
先ほどの解説にもあったように、日本の平均停電時間は19分と他国と比べても非常に優秀な数値を誇っています。そのため「日本ではスマートグリッドを推進する必要はないのでは?」と考える人もいるでしょう。
しかし日本はヨーロッパと同じく、エネルギー自給率が低いです。
主要国のエネルギー自給率比較(2017年)
出典:資源エネルギー庁「日本のエネルギー2018 「エネルギーの今を知る10の質問」
そのため、海外輸入に頼らない風力発電や太陽光発電を大量導入する必要があります。現在では再生可能エネルギーやZEH(ゼッチ:スマートメーターやHEMSを搭載した住宅)の普及が少しずつ進んでおり、エネルギーの自給自足に向かっています。
5. まとめ
いかがだったでしょうか?スマートグリッドが如何に環境において、そして経済において重要な役割を担いつつあるかが分かったかと思います。やはりエコを意識する上で大切なのは、まずは現状の消費量を把握することです。現代の我々で協力して、次世代の人々が住みやすい地球にしていきましょう。