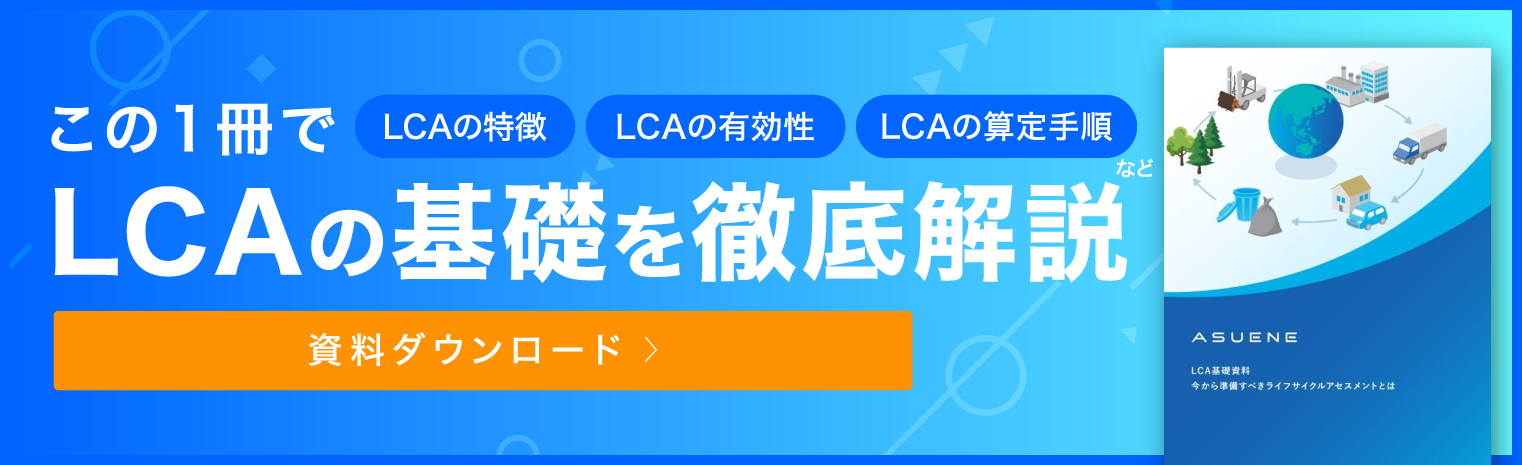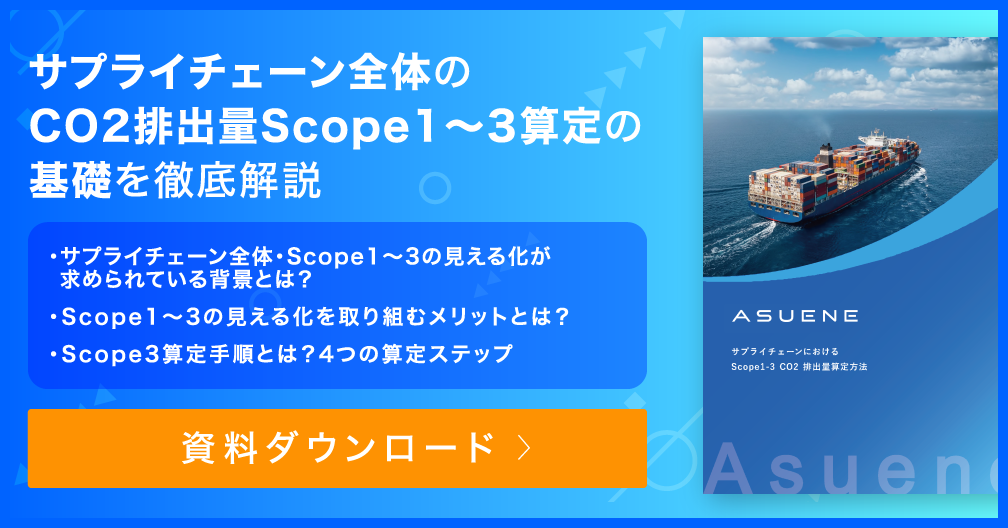カーボンフットプリント(CFP)義務化を巡る動向を解説
- 2024年06月27日
- CO2算定
カーボンフットプリント(CFP)の義務化は、気候変動対策の重要な取り組みとして、世界で注目を浴びています。カーボンフットプリントとは、製品やサービスのライフサイクルを通して排出されるCO2の量を指し、それを数値化することで環境への影響を具体的に把握するための指標となります。
ここでは、カーボンフットプリントの意味や日本や世界のカーボンフットプリントを巡る状況、今後の日本のカーボンフットプリント義務化を巡る動向などをご紹介します。
目次
-
カーボンフットプリント(CFP)とは
-
EU カーボンフットプリント表示の義務化
-
日本のカーボンフットプリント義務化を巡る今後の動向
-
まとめ:国際的な環境貢献基準でカーボンフットプリント義務化に素早い対応を
1.カーボンフットプリント(CFP)とは
カーボンフットプリントとは
カーボンフットプリント(Carbon Footprint of Product)とは、製品やサービスが生産から廃棄までの全過程でどれだけの温室効果ガスが排出するかを示す指標で、製品のライフサイクル全体にわたるCO2排出量を表し、製品が環境にどれだけ影響を与えているのかが分かるものとなっています。
例えば、紙パック牛乳の場合、原料の乳牛の飼育・紙パック生産の「原材料調達」、牛乳製造 ・パッケージングでの「生産」、輸配送 ・冷蔵輸送における「流通・販売」、商品を冷蔵しておく「使用・ 維持管理」、紙パック収集 ・リサイクル処理における「廃棄・ リサイクル」までに排出されるCO2排出量全てがカーボンフットプリントということになります。
出典:経済産業省『サプライチェーン全体でのカーボンニュートラルに向けた カーボンフットプリントを巡る動向』p,9.(2023/09/12)
出典:経済産業省『カーボンフットプリント ガイドライン』p,4.(2023/05/26)
カーボンフットプリントの目的
気候変動は世界の大きな問題で、企業の未来に影響を及ぼすものと考えられており、環境を守り経済を育てていくためにもカーボンフットプリント対策を進めることが重要です。そこで、製品やサービスの原材料の調達から廃棄までの全過程で発生するCO2の量を計算することで、企業は自社の製品やサービスが関わるサプライチェーンの中で、どの段階でCO2削減に最も効果的に取り組めるかを知ることができます。
そして、カーボンフットプリントをきっかけにライフサイクル全体の環境配慮に取り組むことで、気候変動以外の環境問題への対応能力の向上に期待があります。
出典:経済産業省『カーボンフットプリント ガイドライン』p,7.(2023/05/26)
出典:経済産業省『サプライチェーン全体での カーボンフットプリントの算定・検証等 に関する背景と課題』p,4.(2022/09/21)
カーボンフットプリントの重要性
日本は、気候変動などの環境問題に対応するために2050年までに温室効果ガスをゼロにする「カーボンニュートラル」を目標としており、消費者が環境に優しい製品を消費者が選ぶことで経済と環境の両方を守ることが可能となります。この動きを支えるためには、製品の環境影響を示すカーボンフットプリントがとても重要であり、カーボンフットプリントは製品が環境に与える影響を数値化し、消費者がより環境に優しい製品を選択をする手助けにもなります。
出典:経済産業省『カーボンフットプリント ガイドライン』p,7.(2023/05/26)
2. 世界のカーボンフットプリント(CFP)義務化の現状
カーボンフットプリントの取り組みが進んでいるEUなど、世界ではカーボンフットプリントの義務化が進められています。ここでは、世界のカーボンフットプリント義務化の現状をご紹介します。
世界のカーボンフットプリント活用状況
世界中では、計算されたカーボンフットプリントが実際の市場で使われています。民間企業も気候変動に対処するための国際的なグループに参加し、カーボンフットプリントの活用を促進しています。気候関連リスク・機会について情報開示を推奨する「TCFD」は、賛同する日本のプライム市場に上場している企業に対しては、特にカーボンフットプリントの情報公開を求めており、米国政府が世界経済フォーラムと立ち上げたイニシアチブ「First Movers Coalition」は、賛同する企業にCO2排出量が少ない製品を優先的に購入することを推奨し、それによって全体のカーボンフットプリントを減らすことを目指しています。
また、欧州の小売・食品企業の民間企業コンソーシアム「Foundation Earth」は、農業の段階から販売までの全てのプロセスの中でのCO2排出量を計算し、その製品がどれだけ環境に優しいのかが消費者に分かるようラベル付けをしています。
出典:経済産業省『サプライチェーン全体での カーボンフットプリントの算定・検証等 に関する背景と課題』p,8.(2022/09/21)
一歩先行くEUのカーボンフットプリント義務化
欧州委員会はGHG排出削減の目標達成のために、GHG排出量が多い産業を対象にCFPの新しいルールを作り、これらの産業が排出量を減らすよう促しています。EUでは、特にフランスが先駆けて、衣料品などの製品にカーボンフットプリントを表示することを義務付け、食品に関しても持続可能な表示を目指した取り組みが進められています。
また、EUのバッテリー規制では2024年から対象のバッテリーに対してカーボンフットプリントの表示が義務化となり、特定の基準を超えるカーボンフットプリントを持つバッテリーは市場に出すことが制限されます。
出典:経済産業省『カーボンフットプリント レポート(案)』p,10.11.12.13.(2023/01/30)
3.日本のカーボンフットプリント義務化を巡る今後の動向
最後に日本のカーボンフットプリント義務化を巡る今後の動向をご紹介します。
カーボンフットプリント開示の動きが拡大
日本のGHG排出量の約10~20%は、中小企業からの排出によるものですが、これらの企業の環境対策は不十分である一方で、TCFDやISSBによるサプライチェーン全体のCO2排出量の開示要求が増えており、製品のライフサイクル全体のカーボンフットプリントの計算と公表を行うことを求められる動きが広がっています。
そのため、企業はカーボンフットプリントガイドラインに基づいて、事業者が自分でカーボンフットを計算し理解し、そして、消費者が環境に優しい製品を選ぶことを推奨することで製品のライフサイクル全体のGHG排出量削減を目指します。
出典:経済産業省『サプライチェーン全体でのカーボンニュートラルに向けた カーボンフットプリントを巡る動向』p,10.14.(2023/09/12)
日本製品のグリーン化促進
国や独立行政法人などの機関では、特定の調達物品の全購入分のうちの78.3%を「95%以上を環境に配慮した製品」として購入しています。世界中では、環境に優しい製品への関心が高まっており、そうした「グリーン製品」が国際市場での競争力を持つようになっている中、日本でも国内の公共調達をグリーン化を促すことが重要となります。
これは、日本製品をさらに環境に優しいものにして、そのような製品の購入を進めることで、日本の製品が世界の市場でも成功すると考えられているからです。
出典:環境省『環境物品等の調達の推進に関する 基本方針の変更について』p,9.(2023/03/06)
出典:経済産業省『サプライチェーン全体でのカーボンニュートラルに向けた カーボンフットプリントを巡る動向』p,15.(2023/09/12)
環境ラベルプログラムの推進
サプライチェーン全体における製品のカーボンフットプリントは、その約60%を原材料や中間材が占めており、この結果の信頼性、つまり、製品が環境に与える影響を性格に把握しそれが証明された情報を求める企業や消費者の声が高まっています。環境ラベルは、製品が環境にどれだけ優しいかを示すもので、企業が環境に配慮した製品作りを行う動機付けとしての効果が期待されています。
しかし、この環境ラベルは、企業の自発的な活動であり法的な強制力がないため社会や経済の変化に影響されやすく、また、数値の見える化だけでは製品を環境に優しいと明確にするのは難しいなどの問題もあり、従来のラベルでカバーできていない要求にも対応した「双方向コミュニケーションラベル」の開発を目指しています。
出典:一般社団法人サステナブル経営推進機構『SuMPO/カーボンニュートラルイニシアブ -2030年カーボン価値の実感できる社会づくりを目指して-』p,48.(2021/05/13)
出典:経済産業省『定量型環境ラベルの将来像』p,16.17.(2013/12/17)
4.まとめ:国際的な環境貢献基準でカーボンフットプリント義務化に素早い対応を
カーボンフットプリントは、製品やサービスが生産から廃棄に至るまでの過程で発生するCO2の総量を表す指標で、これにより製品の環境への影響度が明らかになります。世界では気候変動が企業の経営に大きな影響を及ぼすことを問題視していて、カーボンフットプリントの迅速な対応が求められています。そんな中、EUは既にカーボンフットプリントに関する新しいルールを設け、取り組みを進めており、日本でも世界と足並みを揃えた取り組みを求める声が高まりを見せています。
ぜひ、国際基準のカーボンフットプリントのルールの知識を得て、今後のカーボンフットプリント義務化へ対応できる企業を目指しましょう。