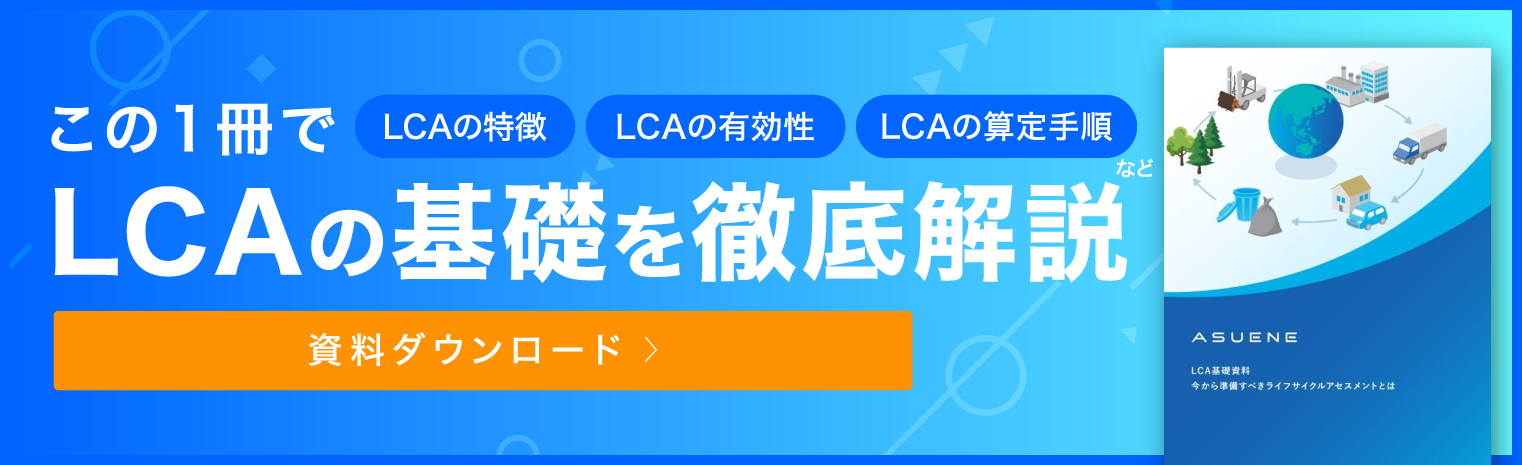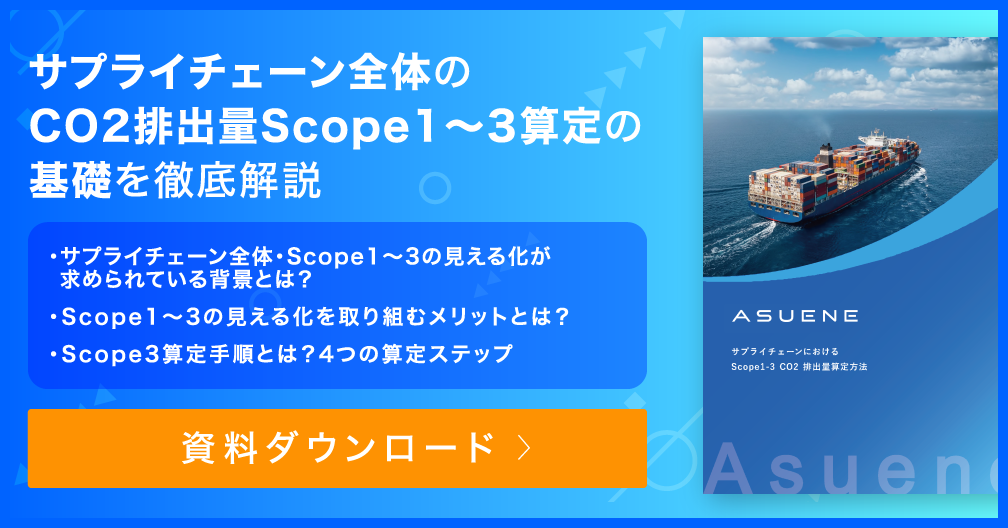TCFDの開示義務化の必要性とプロセスを解説
- 2024年06月25日
- CO2算定
TCFDは、日本では「気候関連財務情報開示タスクフォース」と呼ばれており、気候変動リスクによる企業の財務状況への影響を明確にし、それに対応をしていくための重要な国際的フレームワークです。
TCFDに取り組むことは、気候変動リスクが大きな課題となっている現在において、企業の経営状況を左右するものとなっています。ここでは、TCFDの基礎知識や開示義務が必要とされる理由、重要な4つの要素や開示に有効なシナリオ分析について、TCFD開示企業の事例とともにご紹介します。
目次
-
TCFDとは
-
TCFDの開示に必要な4つの要素
-
シナリオ分析による情報開示方法
-
企業のTCFD情報開示事例
-
まとめ:TCFD開示義務化の必要性を理解し環境貢献に向き合う企業を目指そう
1. TCFDとは
日本でもTCFDに沿った開示を導入している機関が増えており、TDFCの理解を深めることが重要視されています。ここでは、TCFDの意味や特徴をご紹介します。
TCFDとは
TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)とは、企業が気候変動によって直面するリスクと機会を理解し、それらが財務状況に与える影響を公表することを目的とした国際的な枠組みのことです。
TCFDでは、すべての企業に対して、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標の4つの項目の開示を義務化することを求めており、日本は2023年2月の時点で、1,211の企業がTCFDに賛同しています。
次いでイギリスの499社と比べると、日本の賛同企業数は世界で一番となっています。そして、TCFDは2023年、国際会計基準財団(IFRS財団)が設立した国際サステナビリティ委員会(ISSB)にTCFDの提案が採用され、国際的な基準と認められたことで目的達成となり、同年の10月に解散をしています。
出典:環境省『TCFDを活用した経営戦略立案のススメ』p,13.(2023/03)
出典:資源エネルギー庁『企業の環境活動を金融を通じてうながす新たな取り組み「TCFD」とは?』(2019/09/03)
出典:環境省『地域金融機関におけるTCFD開示の手引き』p,9.(2023/04/07)
出典:林野庁『参考資料1 企業によるESG関連情報開⽰の主な枠組み等の概要』p,2.(2024/04/10)
なぜTCFD開示の義務化が必要なのか
気候変動が進めば銀行や保険会社などの金融機関の大きな問題につながり、お金の流れや経済の安定に影響を与える可能性があるとの考えからTCFDが設立されました。
大きなリスクとして、自然災害による直接的な物の破壊やそれによって物流が止まる、資源の枯渇などの間接的な影響(物理的リスク)や、気候変動で被害を受けた人に賠償を請求された場合のリスク(賠償責任リスク)、また、脱炭素社会へと変化する過程でGHG排出量が多い企業に投資されている資産への評価よるリスク(移行リスク)などが挙げられます。
そこで、TCFDでは企業が気候変動のリスクを理解し情報開示をすることで、投資の機会を失うことを防ぐ他、長期的な目線では企業の経営破綻を防ぐ目的があります。
出典:資源エネルギー庁『企業の環境活動を金融を通じてうながす新たな取り組み「TCFD」とは?』(2019/09/03)
出典:環境省『TCFDを活用した経営戦略立案のススメ』p,12.(2023/03)
出典:環境省『金融機関における TCFD 開示に基づくエンゲージメント実践ガイダンス』p,4.(2024/03)
世界のTCFD開示状況
世界のTCFD開示状況を見てみると、欧州、米国、カナダではTCFDに沿った開示が推奨されており、EUと英国では2023年から義務化されている他、米国においても開示義務が検討されています。
また、日本のTCFD開示状況は、TCFD提言に対応するための組織「TCFDコンソーシアム」によると、2019年には同組織の活動に参画している132企業のうち60企業が全てまたは一部の情報を開示していましたが、2020年には166企業のうち85企業が開示しており、より多くの企業が気候変動に関する情報を公表しているという見方ができます。
出典:環境省『TCFDを活用した経営戦略立案のススメ』p,23.24.(2023/03)
出典:経済産業省『TCFD開示を巡る現状と課題』p,20.(2020/05/29)
2. TCFDの開示に必要な4つの要素
TCFD提言には、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4つの重要な要素があります。ここでは、それぞれの要素についてご紹介します。
ガバナンス
ガバナンスでは、企業が気候変動によって直面するリスクや得られる利益について、どのように管理するのかを明らかにすることが求められています。具体的には、取締役会がどのように気候変動のリスクと機会を管理してるかについて説明したり、企業が気候変動の影響に備え、それをビジネスの成長としてつなげるための評価をしそれに対応する計画を考える経営陣の役割の情報などを開示します。
出典:環境省『地域金融機関におけるTCFD開示の手引き』p,12.(2023/04/07)
出典:環境省『TCFDを活用した経営戦略立案のススメ』p,16.(2023/03)
戦略
戦略では、短期・中期・長期の目線において企業が気候変動によって直面するリスクや機会が事業運営や長期経営にどのような影響を及ぼすかを評価し、その影響が重要だと判断された場合には、その情報を公開するものとしています。また、地球の平均気温を2℃以下に抑えるに向けて、さまざまな環境変化が起こった場合に、企業がそれに対してどのように対応し、影響を最小限に抑えるかを検討します。
出典:環境省『地域金融機関におけるTCFD開示の手引き』p,12.(2023/04/07)
出典:環境省『TCFDを活用した経営戦略立案のススメ』p,16.(2023/03)
リスク管理
リスク管理は、気候変動に関連するリスクの識別、評価、管理の状況を説明するもので、これは、企業が気候変動に関連するリスクをどのように見つけ、その重要性をどう評価し、それらのリスクに対してどのように対処していくのかを明らかにします。
出典:環境省『地域金融機関におけるTCFD開示の手引き』p,12.(2023/04/07)
出典:環境省『TCFDを活用した経営戦略立案のススメ』p,17.(2023/03)
指標と目標
指標と目標では、企業が気候変動の影響をどのくらいしっかりと考えているのか、また、それに対しての具体的な行動計画が求められています。その中には、企業が自社の活動によって直接的(Scope1・Scope2)または、間接的(Scope3)に発生するGHG排出量と、それらがもたらす可能性のあるリスクを明らかにし報告することなどが含まれています。
出典:環境省『地域金融機関におけるTCFD開示の手引き』p,12.(2023/04/07)
出典:環境省『TCFDを活用した経営戦略立案のススメ』p,17.(2023/03)
3. シナリオ分析による情報開示方法
TCFDによる情報開示にはシナリオ分析が有効な手立てとなります。ここでは、シナリオ分析の意味や、具体的なステップをご紹介します。
シナリオ分析とは
シナリオ分析とは、未来の不確かな状況に備えて企業が長期的な計画を立てるのに有効な方法で、気候変動のリスクに不安がある企業は、将来起こるかもしれない問題に備えて事前に対策を考えておくことが重要です。
具体的には、将来が予測されるような考え方の場合、企業が未来の変化に適応する能力が不足しており、計画にも一致が見られないため、困難な状況に立ち向かう力があるかどうか不確かです。しかし、予測不可能でさまざまなことが起こり得る未来を考えた場合、未来の変化にも適応できる経営力で客観的に未来を見据えた計画を立てることで困難に立ち向かえる企業となります。
出典:環境省『TCFDを活用した経営戦略立案のススメ』p,27.(2023/03)
ステップ1:リスク重要度の評価
企業にとってのリスクを特定し、それらがもたらす影響を評価して、どのリスクを重視して対応するのかを決めます。具体的には、事業やプロジェクトに影響を与える可能性のあるリスクをリストアップしたり、リスクが実際に起こった場合に、具体的な数字やデータに頼らずにリスクの結果を説明する、リスクの優先順位を見極めそれに応じて対応していく計画を立てることなどが挙げられます。
出典:環境省『TCFDを活用した経営戦略立案のススメ』p,61.62.(2023/03)
出典:環境省『地域金融機関におけるTCFD開示の手引き』p,36.(2023/04/07)
ステップ2:シナリオ群の定義
地球の温度上昇を最小限に抑える目標を含む複数のシナリオから最適なものを選び、それに必要なデータ情報を収集し、全体のコンセプトや背景を明確にしていきます。ポイントとしては、特定の条件や状況をもとで、将来に何が起こるのか、また、世界がどのような方向に進むのかをしっかりと理解して把握し、必要に応じて外部の意見を取り入れて、社内で共通の理解を築くことが重要です。
出典:環境省『TCFDを活用した経営戦略立案のススメ』p,64.65.66.(2023/03)
出典:環境省『地域金融機関におけるTCFD開示の手引き』p,40.(2023/04/07)
ステップ3:事業インパクト評価
事業インパクトとは、投入コストや事業コスト、利益、サプライチェーンなどのことで、事業の成功や持続可能性を評価する際の重要な要素であり、事業インパクト評価では、それぞれの異なる状況が、企業の計画や財政にどのように作用するかを理解し評価します。これは、リスクと機会を数値化し、その数値を使って企業の財務への影響を推測したり、予測や計算を通じて、未来のビジネスがどのように変化する可能性があるのかを理解するものです。
出典:環境省『TCFDを活用した経営戦略立案のススメ』p,71.72.73.(2023/03)
出典:環境省『地域金融機関におけるTCFD開示の手引き』p,41.(2023/04/07)
ステップ4:対応策の定義
自社が直面している重要なリスクやチャンスをしっかりと理解し、それにどのように対応しているのかを把握し、場合によっては他の競合企業の対応策の情報を入手します。そして、問題に対する適切な解決策を考え、具体的な行動を取るためにしっかりとした体制を整え、将来に向けてどのような計画を立てるべきなのかを検討します。
出典:環境省『TCFDを活用した経営戦略立案のススメ』p,81.82.(2023/03)
ステップ5:情報開示をする
TCFDのガイドラインに沿って、比較表やリストを通して企業が気候変動に関するリスクと機会の分析方法とその結果を報告し、TCFD提言の開示項目とシナリオ分析の関係性を説明します。この情報開示は、各ステップの検討結果を記載することで、適切な情報を公開し、企業の評価や信頼性の向上につながります。
出典:環境省『TCFDを活用した経営戦略立案のススメ』p,86.87.88.(2023/03)
4. 企業のTCFD情報開示事例
ここでは、企業のTCFD情報の開示事例をご紹介します。
積水ハウス株式会社
積水ハウス株式会社は、1.5℃の温暖化シナリオに基づいた分析を行い、事業に影響を及ぼす重要なリスクと機会を特定し、財務への潜在的影響と対策を明らかにしています。そして、分析で見つかった重要な財務リスクは引き続き監視を続け、リスク管理と分析の制度を高めながら対策を強化するとともに、新しい子会社のリスク評価も改善し、持続可能な社会への貢献を目指しています。
出典:気候変動適応情報プラットフォーム『TCFD提言に沿った情報開示(2023年度) :積水ハウス株式会社』(2023/12/04)
ヤマトホールディングス株式会社
ヤマトホールディングス株式会社は、気候変動はビジネスの中断や施設の損害を引き起こし、投資とコストの増加の懸念があるという考えからTCFD開示に取り組んでいます。シナリオ分析では、まずリスクと機会を把握し(ステップ1)、次に気候シナリオを設定(ステップ2)、そのシナリオに基づいて事業影響を評価(ステップ3)、最後に対策を策定(ステップ4)しています。今後は、災害の発生条件を詳細化し事業評価を再評価して対応策を進化させるとともに、リスクと機会に関しても引き続き取り組んでいきます。
出典:気候変動適応情報プラットフォーム『TCFD提言に基づく情報開示 :ヤマトホールディングス株式会社』(2023/06/15)
小野薬品工業株式会社
小野薬品工業株式会社は、TCFD提言に沿って1.5℃と4℃の温暖化シナリオを使用して、医薬品製造業の気候変動リスクと機会を分析しました。1.5℃のシナリオではIEAの「持続可能な開発シナリオ」を、4℃のシナリオではIPCCの「RCP8.5シナリオ」とIEAの「公表政策シナリオ」をもとに設定し、2020年から2030年にかけて、国内外の工場、委託先、サプライヤー、投資家、顧客、人材採用を分析します。
これにより、リスクの発生時期、確立、影響範囲を分析し、対策を評価して優先順位を設定し、会社全体のリスク管理に統合するとともに、分析結果で特定した水リスクに関しては、取引先との連携を強化し複数の供給源を確保しながら、気候変動リスクを取引先選定に組み入れることを検討します。
出典:気候変動適応情報プラットフォーム『気候変動に関するリスク・機会の分析・評価 :小野薬品工業株式会社 | TCFDに関する取組事例』(2022/08/22)
5. まとめ:TCFD開示義務化の必要性を理解し困難にも立ち向かえる企業を目指そう
TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)は、企業が気候変動のリスクと機会を評価し、それらが財務に与える影響を開示するための国際的フレームワークであり、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4つの重要な分野に関する情報の提供が求められています。
情報開示にはシナリオ分析が有効であり、多くの企業がTCFDの開示の際に導入しています。ぜひ、TCFD開示の義務化の必要性を理解して、未来に向けてしっかりと準備をし、どんな困難にも立ち向かえる企業を目指しましょう。