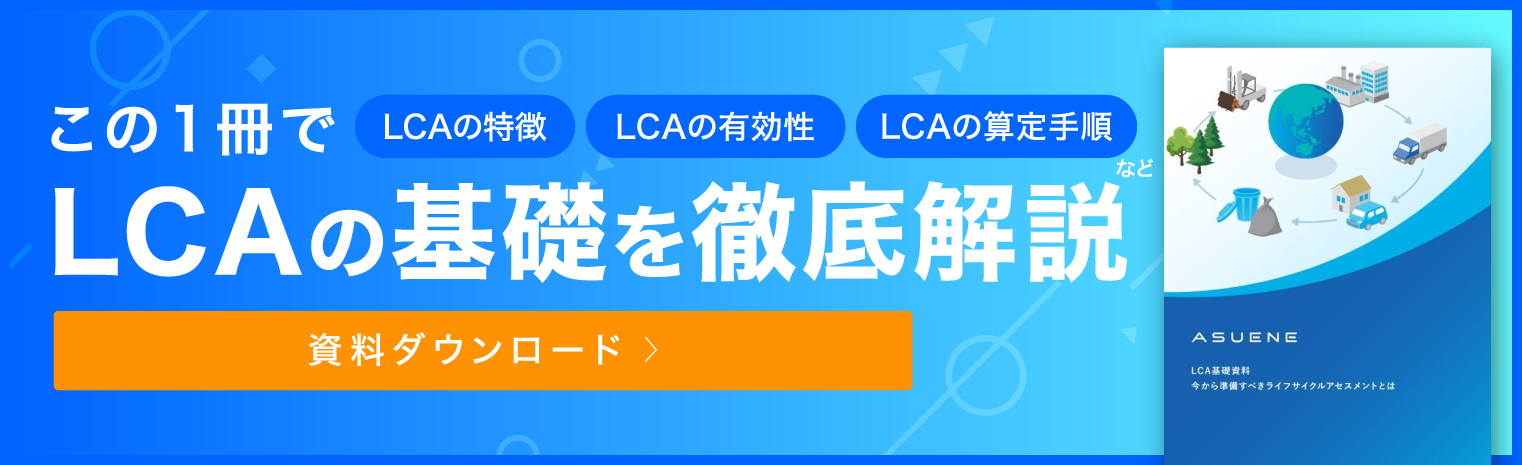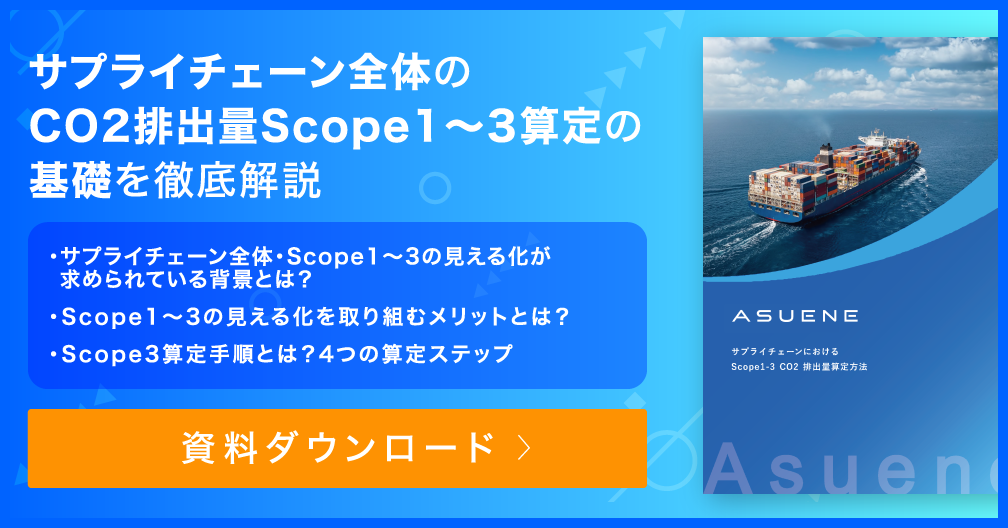【2024年最新】日本における発電量の構成割合は?再エネ発電普及のポイントを解説
- 2024年02月02日
- 発電・エネルギー

日本における発電割合は、2022年度の発電実績によると、化石燃料によるものが72.7%である一方、再生可能エネルギーによるものは21.7%と、いまだに化石燃料への依存度が高くなっています。社会としての脱炭素化を考えるうえでは、非化石燃料である再生可能エネルギーによる発電への移行が優先度の高い課題であると言えるでしょう。
本記事では電力供給方法に関する世界の潮流や日本の現状、今後重要視される再生可能エネルギーについてわかりやすく解説します。
目次
-
-
日本におけるエネルギー発電の構成割合
-
再生可能エネルギーとは
-
日本における発電割合の向上が期待される再生可能エネルギー
-
日本で再生可能エネルギーによる発電割合を上昇させるために
-
まとめ:再生可能エネルギーを導入してカーボンニュートラルを達成しよう!
-
1. 日本におけるエネルギー発電の構成割合
日本では、2050年までにカーボンニュートラルを実現するという宣言がされました。そのためには、温室効果ガス発生の原因となる、化石燃料による火力発電量を削減することが必要です。ここでは日本のエネルギーごとの発電割合を、世界の発電割合と比較しながらご紹介します。
(1)日本の発電割合
2022年度における発電割合は、石油によるものが8.2%、石炭が30.89%、天然ガスが33.7%となっており、エネルギー供給は化石燃料による火力発電が72.7%を占めています。日本は火力発電に電力供給の多くを頼っていますが、火力発電は化石燃料を燃焼する際に温室効果ガスを排出しており、地球温暖化に影響を及ぼします
一方、温室効果ガスを排出しない発電方法では、原子力発電が5.6%(対前年1.3%減)、再生可能エネルギーが21.7%(同1.4%増)となっています。原子力発電と再生可能エネルギーを合わせた非化石燃料による国内発電割合は27.3%であり、3割にも達していません。温室効果ガスの発生抑制のためには、非化石燃料による発電量の割合をさらに増やしていく必要があります。

出典:経済産業省『2022年度エネルギー需給実績(速報)』p4,5
再生可能エネルギーのうち、最も発電割合が高いのは太陽光発電で、2022年度の全発電量に占める割合は9.2%です。次に高いのは水力発電で、7.6%を占めています。

出典:資源エネルギー庁『集計結果又は推計結果(総合エネルギー統計)「時系列表」』
(2)再生可能エネルギーの普及とFIT
2012年のFIT制度の導入により、再生可能エネルギーによる発電設備の導入量が大幅に増加しました。FIT制度(固定価格買取制度)とは、再生可能エネルギーで発電した電力を電力会社が買い取る制度で、利用者が賦課金を払う形で運用されています。
2021年度における日本の再生エネルギー導入容量は138GWで世界第6位、このうち太陽光発電容量は78GWで世界第3位となっています。しかし太陽光発電に適した設置場所の減少などにともない、新たに認定される容量は年々縮小傾向にあります。既に平地面積あたりの太陽光設備容量は470kW/平方メートルと主要国でも最大となっており、今後は公共施設等の屋根への太陽光発電設備の設置など、地域と共生した取り組みが求められています。
出典:資源エネルギー庁『太陽光発電について』p7(2022/12)
出典:資源エネルギー庁『エネルギーの安定供給の再構築に向けた 再エネ政策の方向性について』p25(2022/12/6)
(3)世界との比較
それでは、世界と比べて日本の発電割合はどのようになっているのでしょうか。
自然エネルギー財団が発表した2022年の「世界の電源構成」によると、日本をはじめとするアジアでは約60~70%を石炭・石油・ガスなど化石燃料による火力発電に頼っているのに対して、ヨーロッパやアメリカ大陸では自然エネルギー発電(再生可能エネルギー発電)の割合が高い国が多くなっています。特にデンマークやブラジルでは、再生可能エネルギーの割合が約80〜90%に及びます。

EUでは気候変動の対策として、欧州グリーンディールなど様々な取り決めを行っていることもあり、非化石燃料による発電が進んでいる国が多くあります。また2021年から続くウクライナ侵攻では、世界各国でエネルギー危機が生じ、特にヨーロッパでは早急な再生可能エネルギーへの転換が迫られています。
出典: ISEP『2021年の自然エネルギー電力の割合(暦年・速報)』 (2022/4/4)
2. 再生可能エネルギーとは
非化石燃料である再生可能エネルギーによる発電の普及拡大が、社会の脱炭素化において非常に重要です。再生可能エネルギーについて、その種類などを解説します。
(1)再生可能エネルギー発電とその特徴
再生可能エネルギーとは、太陽光や風力など、自然界にあって枯渇することなく永続的に利用することのできる熱・バイオマス(生物資源)のことです。政令では
太陽光や風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマスなどが含まれるとされています。
再生利用可能エネルギーのメリットとしては、資源が枯渇しないことや、温室効果ガスを排出しないこと、国内で生産が可能であるため、エネルギー自給率が向上することが挙げられます。一方デメリットとしては、発電コストが高いことや、天候に左右されるものでは発電量が不安定なことなどが挙げられます。
(2)再生可能エネルギーの導入加速化が必要な理由
日本において再生可能エネルギーの導入加速化が必要であることには、以下のような理由があります。
・温室効果ガスの削減
・エネルギー自給率の向上
・化⽯燃料調達に伴う資⾦流出の抑制
・産業の国際競争⼒の強化
・雇⽤の創出
・地域の活性化
・⾮常時のエネルギーの確保
世界各国においても同様の背景から、再生可能エネルギービジネスへの投資や雇用が増加しています。再生可能エネルギーの普及には環境対策だけでなく、経済成長のドライバーとしての役割も期待されます。
出典:環境省『低炭素社会づくりのためのエネルギーの低炭素化に向けた提言』p1,11
3. 日本における発電割合の向上が期待される再生可能エネルギー
ここでは、日本国内で特に発電割合の向上が期待されている、再生可能エネルギーによる発電方法を2つご紹介します。
(1)水素発電
再生可能エネルギーによる発電の内、日本でも特に注目されているのが、ほぼCO2を発生させない、水素を利用した発電方法です。水素は燃焼時にCO2を排出しないため、再生可能エネルギーによって水素を作ることができれば、製造から燃焼までCO2を排出しない「CO2フリー」なエネルギーとなるのです。
水素を利用した発電方法は2種類あります。
・発電用途:水素を燃焼することで、発電機を駆動し発電
・燃料電池:水素と空気中の酸素との化学反応で発電
化石燃料による発電の代替として期待されているのは、発電機を用いる発電用途です。特にガスタービン内で化石燃料の代わりに水素を燃焼させ、発電機を駆動するガスタービン発電は、最大30MW程度の出力が見込まれており、国内各社による実証実験が行われています。
中でも化石燃料と混合して水素を燃焼させる「水素混焼発電」は、既存のガスタービン技術でも可能と考えられています。水素発電は膨大な水素を利用するため、水素混焼発電が実用化すると水素の市場規模が拡大し、水素の低価格化につながることが期待されています。なお、水素のみの水素発電は水素専焼発電と言います。
出典:環境省『水素関連基礎情報資料』p23,26
出典:日本経済新聞社『水素混焼発電機』
(2)地熱発電
地熱発電は、地下のマグマの熱で温められた水蒸気がタービンを回し発電する方法です。地熱発電は、太陽光や風力のように気候によらないため安定した電気エネルギーとなりますが、地熱資源量は地下を掘ってみなければわからないというリスクを持ち合わせています。しかし、日本は世界第三位の資源量を持っているため、この豊富な資源を活用した持続的な再生可能エネルギー発電に期待が集まっています。
出典: 資源エネルギー庁『もっと知りたい!エネルギー基本計画④ 再生可能エネルギー(4)豊富な資源をもとに開発が加速する地熱発電』(2022/3/23)
出典: 自然エネルギー財団『発電量内訳』(2021/1/21)
4. 日本で再生可能エネルギーによる発電割合を上昇させるために
最後に、今後日本の再生可能エネルギーによる発電割合を上昇させるにはどうすればよいでしょうか。企業や個人の方の取り組みを紹介し、今後の見通しを紹介します。
(1)再生可能エネルギーの企業による積極導入
2019年、中小企業向けに「再エネ100宣言RE Action」が発足されました。参加企業は再エネ100%に向けて目標を対外的に公表し、実践することで再エネ100%を目指す枠組みです。
主に、自家発電や小売電力会社からの購入(自敷地内での発電含む)、J-クレジットの購入などの取り組みが行われています。J-クレジットとは、省エネ機器の導入や森林経営などの取り組みによる温室効果ガスの削減量を、国が「クレジット」として認証し売買を可能にする制度です。RE100では、太陽光発電やバイオマス発電など、再エネ電力由来のJ-クレジットを、再エネ調達量として報告することができます。
(2)個人での再生可能エネルギー発電の利用
住宅への太陽光発電導入件数は、一般社団法人太陽光発電協会によると2022年度の新規導入件数は190,307件で、前年から37,206件増加しています。増加の主な要因は、燃料価格の高騰と円安で上昇した電気料金に対して競争力が高まったことと考えられますが、新築住宅の着工件数は今後減少していく見込みとも言われており、「2030年迄に新築住宅の6割に設置する」という日本国政府の目標達成に対しては、さらなる対策が必要と言えます。
出典: 一般社団法人 太陽光発電協会『太陽光発電の現状と自立化・主力化に向けた課題』(p21)(2023/10/27)
(3)今後の日本の再生可能エネルギー発電の見通し
再生可能エネルギー発電の研究開発は、洋上風力・水素・アンモニアエネルギーに関するものが盛んに行われています。中でも洋上風力は、欧州企業も参入し、日本の大手企業との連携も期待される分野です。
再生エネルギー分野への企業の参入には、グリーンイノベーション基金という制度があります。これはNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)に造成された2兆円超の基金で、カーボンニュートラルへ向けた野心的かつ具体的な目標にコミットする企業等に対して最長10年間、研究開発・実証から社会実装までを継続して支援するというものです。他にも省エネ再エネ高度化投資促進税制や、環境・エネルギー対策資金など、再生エネルギー導入を促進する各種の支援制度があります。
出典: 資源エネルギー庁『各種支援制度』
5. まとめ:再生可能エネルギーを導入して、カーボンニュートラルを達成しよう!
ここまで、日本における発電割合と再生エネルギーの特徴・種類・取り組みをご紹介しました。日本では再生可能エネルギーの発電割合は3割弱で、いまだに電力の大半を化石燃料に依存しています。これは他の主要国と比較しても立ち遅れており、再生可能エネルギーによる電力供給割合を引き上げていく必要があります。国としても再生可能エネルギーの普及に注力しており、各企業が再生可能エネルギーの導入を検討する際は、さまざまな支援制度があります。
これらを活用し再生可能エネルギーの利用を拡大して、カーボンニュートラルを実現しましょう!