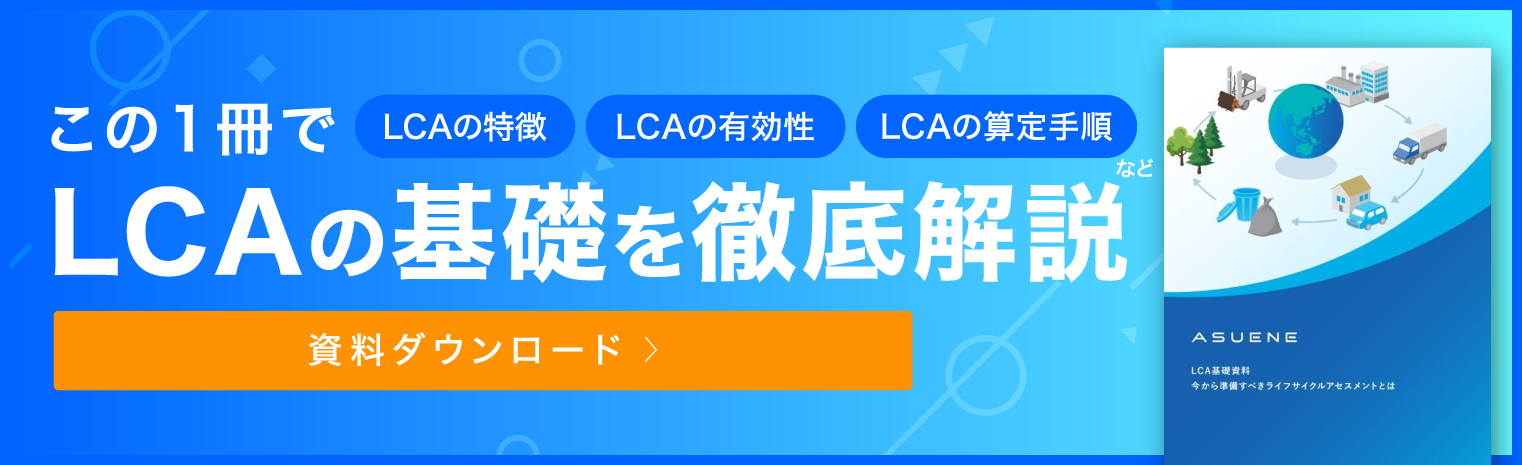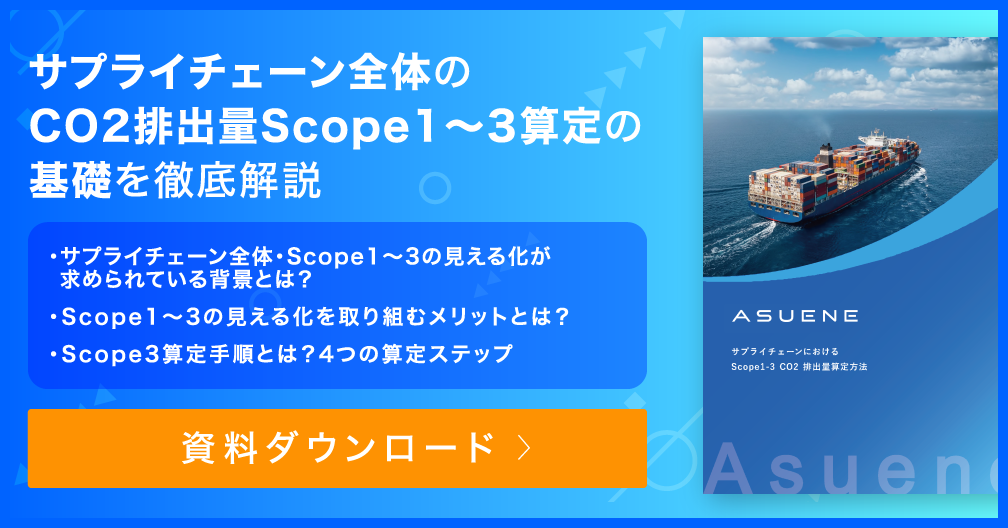中小水力発電に注目!日本の水力発電の割合と将来の発展性
- 2022年06月15日
- 発電・エネルギー

水力発電は、CO2を排出しない再生可能エネルギーのひとつです。日本では明治時代から開発され、エネルギーの供給割合としては7.7%と高くはありませんが、純国産のエネルギーとして日本のエネルギー政策を支えてきました。近年は大規模なダムによらず、中小水力発電の建設が増えてきています。日本の水力発電について、その割合や位置付け、今後の発展性について解説いたします。
目次
-
日本の電源構成における水力発電の割合
-
4種類も存在?水力発電のしくみと種類
-
水力発電のメリットとデメリット
-
日本の水力発電の未来とは?FIP制度と水力導入事例
-
まとめ:水力発電は再生可能エネルギーの選択肢となる
1. 日本の電源構成における水力発電の割合
地球温暖化の原因となる温室効果ガス削減の必要性から、世界的に再生可能エネルギーへの転換が広がっています。政府は2050年カーボンニュートラルを表明し、実現に向けて現在の輸出に頼る化石燃料を減らし、再生可能エネルギーを主たる電源とすることを決めました。
太陽光発電だけでない、再生可能エネルギーの種類
再生可能エネルギーといえば、太陽光発電や風力発電を思い浮かべますが、ほかにも水力発電、地熱発電、バイオマス発電等があります。太陽光はさまざまな場所に設置ができ、災害に強い。風力は海の上でも設置が可能で夜間でも発電できるというメリットがあります。一方で、どちらも発電量が天候に左右されるというデメリットがあります。
全体の7.7%。再エネの4割以上を占める水力発電
水資源が豊かな日本では、水力発電が明治時代から発展し、水力発電導入量では世界第6位となっています。また、2019年度の国内における電源構成では、水力発電は全供給量の7.7%となっています。

出典:資源エネルギー庁「日本のエネルギー2020年度版『エネルギーの今を知る10の質問』」(2020)
全エネルギー供給量における水力発電の割合は決して高くありませんが、再生可能エネルギー全体が18%の中では4割以上を占め、果たす役割は大きいといえます。水力発電は、化石燃料の価格変動のようなリスクがなく、国内で安定的に供給ができるという点で優れています。
現在では、中小水力発電の建設が活発化しており、再生可能エネルギーとして一般にもひろがりを見せています。

出典:資源エネルギー庁『【第213-2-21】日本の水力発電設備容量及び発電電力量の推移』(2021)

出典:資源エネルギー庁『【第213-2-22】水力発電導入量の国際比較(2019年末):IRENA「Renewable Energy Statistics 2019」を基に作成』(2021)
2. 4種類も存在?水力発電のしくみと種類
水力発電は、ダムを思い浮かべることが多いですが、どのように電気が作られ、どのような種類があるのでしょうか。
水力発電のしくみ
水力発電は、水が高いところから低いところへ流れ落ちる勢いによって水車を回して電気を作ります。落差が大きいほど、流れ落ちる水の量が多いほど作られる電気の量は増えます。
出典:資源エネルギー庁『電気の出来る仕組み - 水力発電について』
水力発電の種類
-
貯水池式
大きな池に河川水を貯め、その貯めた水を使って発電します。河川の水の量は季節によって変わりますが、大きな池に溜め込むことによって、電力需要が大きくなる時期でも安定した発電ができます。
-
調整池式
電気の消費量の増減に合わせて池に溜める河川水量を調整し発電します。
-
流れ込み式
河川を流れる水を貯めずに、流れをそのまま発電に利用します。
-
揚水式
電力消費の少ない夜間に下池から上池に水をくみ上げ、日中のピーク時に上池から下池に水を落として発電します。池の水を繰り返し使用する発電方法です。
貯水池式、調整池式、揚水式は需要の変動に応じて稼働量を調整できるのに対し、流れ込み式はほぼ一定の出力で稼働するという特徴があります。
3. 水力発電のメリットとデメリット
安定・クリーン・純国産。水力発電のメリット
電力消費は季節、天候によって、また1日の中でも大きく変化します。水力発電は他のベースロード電源と比べても発電開始に時間を要せず安定した電気を供給することができます。また、CO2を出さないクリーンなエネルギーです。設備寿命が長く、長期にわたる稼働が可能です。
日本は早くから水力による発電を開始し、高い技術力を確立してきました。石炭、石油等の化石燃料を輸入に頼って発電する状況にあって、水力発電は水に恵まれた日本の純国産エネルギーとして重要な役割を担ってきたのです。
手続きが煩雑でコストもかかる……水力発電のデメリット
水力発電は、事業を導入するにあたり、河川に関する調査や環境への影響調査、国土交通省への登録または許可等、河川法に関わる手続きが必要です。また、地域住民の理解を得ることも重要です。さらに、大規模な発電所の立地が開発済みで、中小水力発電で開発できる地点は奥地にあることが多いため、コストがかかる点も懸念材料です。しかし、国の支援事業を活用することができます。
4. 日本の水力発電の未来とは?FIP制度と水力導入事例
FIT制度と、2022年度から始まるFIP制度。水力発電は適性が高い
・FIT制度
FIT制度とは、再生可能エネルギーの固定価格買取制度で、再生可能エネルギーの普及のため、電力会社が電気を一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。買取の対象となる再生可能エネルギーは、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスの5つです。買取に要した費用は再生可能エネルギー発電促進賦課金として一般の電気使用者から広く集められています。

・FIP制度
2022年度から、売電時の価格が市場連動型となるFIP制度が導入されることになりました。再エネ発電事業者は自身で卸電力取引市場や相対取引において売電した価格に「プレミアム」を上乗せされた合計分を収入として受け取ることができる制度です。
これは、電力需要と発電量のピークのずれを解消するとともに、再エネ発電事業者に対し、投資インセンティブを確保し、蓄電池併設等によって、電力需要に応じた電力供給を促すことを目的としています。また、賦課金の国民負担を抑制することにもつながります。
この制度を導入することによって、再生可能エネルギーが競争力を伴う産業へと進化し、ひいては主力電源となることが期待されています。
太陽光や風力発電は天候の影響で供給量の調整が難しく、FIP制度を上手に活用するには蓄電池などの調整設備が必要になります。一方で、水力発電は比較的安定した供給力と、需要に合わせた出力調整が可能です。そのため需要・市場価格が高いタイミングでの売電が可能となり、FIP制度への適性が高いとされています。

出典:資源エネルギー庁『再エネ | 日本のエネルギー 2020年度版 「エネルギーの今を知る10の 質問』
出典:資源エネルギー庁「『エネルギー白書2021』第3部 第3章 第1節 競争力のある再エネ産業への進化 」
大規模発電から中小水力発電へ、導入が活発化
狭い国土に高低差の大きな河川が豊富な日本は、130年以上に及ぶ水力発電の歴史があります。大規模なダム等の水力発電所はすでに開発済みです。一方で大規模な構造物を必要としない中小水力発電は導入が活発になっています。
これらの規模には厳密な定義はありませんが、一般に出力が10,000〜30,000kWのものを中小水力発電、1,000kW以下のものを小水力発電と呼ぶことが多いとされています。
中小水力発電の事例、河川の流水や農業用水を利用
・水の戸沢小水力発電所
水の戸沢の高低差を利用した、東京都檜原村の地元の企業による水力発電です。ノウハウや課題は国の施策を活用した支援を受け、事業化を実現しました。売電収入は次の小水力発電事業の資金や、地域の雇用、課題解決に活用することが検討されています。

出典:資源エネルギー庁『檜原水力発電株式会社(水の戸沢小水力発電所)』
出典:資源エネルギー庁『国の支援施策活用等事例集 | 再エネガイドブックweb版』
・百村第一・第二発電所
栃木県那須塩原市に設置されている百村第一・第二発電所は農業用水路の落差を利用した発電です。発生した電力は一旦電力会社に送電され、運営する野ヶ原土地改良区連合の送・配電線を利用して供給されます。最大出力は合計で120kWです。
出典:国土交通省『小水力発電設置のための手引き』PDF P14
このように河川の流水を利用するだけでなく、農業用水やダムの未利用水、上下水道を利用したものもあります。また、発電の構造では、低落差でも高効率な”らせん”水車や、減圧バルブによる水圧を利用するもの等があります。中小水力発電はまだまだ開発の余地があり、発展性、将来性が期待されています。
5. まとめ:水力発電は再生可能エネルギーの選択肢となる
水力発電はCO2を発生しない環境にやさしいエネルギーです。水資源が豊富な日本では、今後中小水力の発展が大いに期待されます。
水力発電は天候や季節に関わらず、安定的な発電が見込まれ、災害時にも事業を継続することが可能となります。太陽光発電は立地に適した土地が少なくなりつつあると言われています。導入費用が割高でも、稼働年数は数十年と長期間に渡り、今後FIP制度において投資回収の予見可能性も高いことを考慮すると、水力発電は選択肢の一つになるのではないでしょうか。
地域や事業形態に合わせ、エネルギーも分散させることは、リスクの軽減になるでしょう。自治体と協力することで電気の地産地消を可能にし、地域活性化への貢献もなしえるでしょう。再生可能エネルギーの導入を検討されるなら、事業形態、周辺環境、自治体の連携等を考慮し、選択肢を広げてみてはいかがでしょうか。