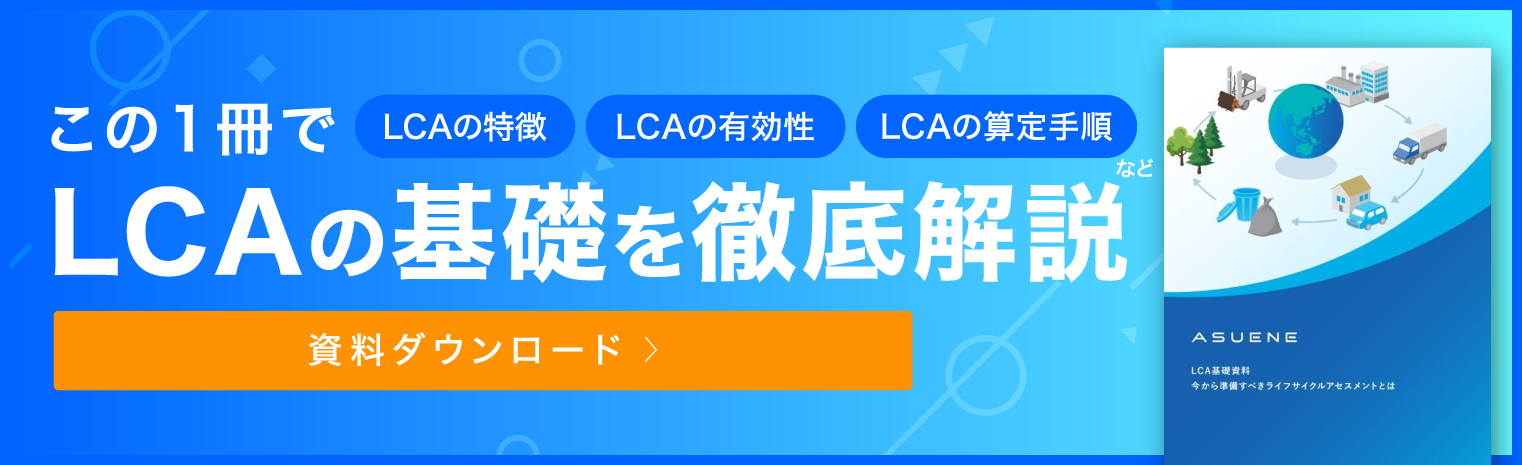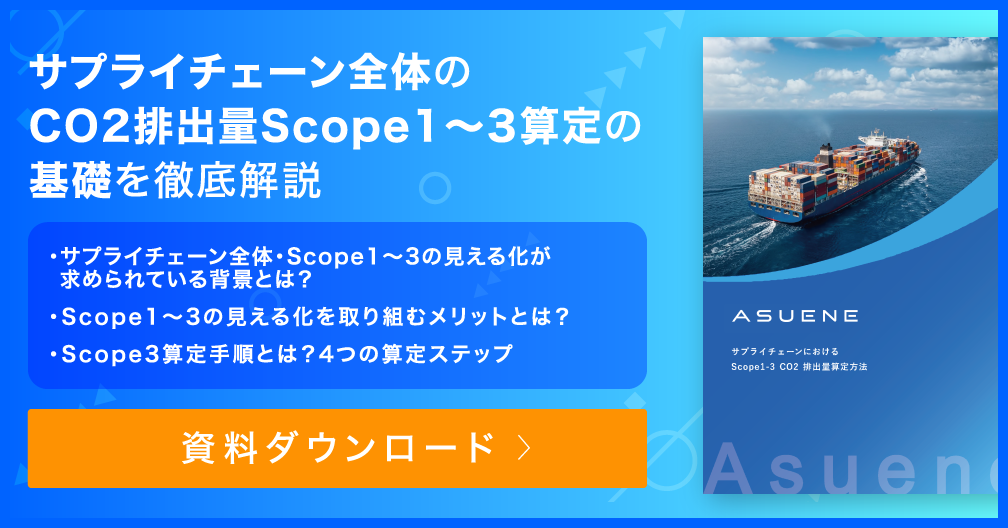EU ETSとは?基礎知識や今後の動向について解説
- 2024年05月22日
- CO2削減
EU ETSとは、EUにおける排出量取引制度のことで、国際的な温室効果ガス取引制度の先駆けとして導入されました。EU ETSは、いくつかのプロセスを進めながら、現在は第4フェーズを進行中ですが、常に環境貢献の高みを目指しており、日本のGXリーグでもEU ETSの考えを参考にするなど、この活動は世界でも注目されています。
ここでは、EU ETSについて基礎知識をはじめ、EU ETSの取引方法や日本企業への影響、気になる今後の動向などをご紹介します。
目次
-
EU ETSとは
-
EU ETSの取引方法
-
気になる今後のEU ETSの動向
-
まとめ:EU ETSの知識を深め海外でも通用する環境貢献を目指そう!
1.EU ETS(EU排出量取引制度)とは
はじめに、EU ETSの基礎知識や設立された背景、気になる日本企業への影響をご紹介します。
EU ETSとは
EU ETSとは、EUが気候変動と戦うために始めた、世界で最初の国際的な温室効果ガスの取引制度で、地球温暖化を防ぐために重要な手段とされています。EU ETSは、企業ごとに排出枠(キャップ)を設け、その枠内で排出を義務付けすると同時に、余剰分や不足分を市場で取引(トレード)できる「キャップ・アンド・トレード」制度を導入しており、2005年の開始からいくつかの段階を経て、現在は第4取引フェーズを進行中です。
出典:環境省『国内排出量取引制度について』p,3.(2013/6/29)
出典:『欧州連合域内排出量取引制度の解説』p,12.14.(2019/03/26)
出典: European Commission『What is the EU ETS? 』
EU ETSが設立された背景
EU ETS設立の理由として、1997年に京都議定書が採用され、先進国37ヵ国は温室効果ガス排出を削減する法的義務を負い、これにより、EUは目標を達成するために、具体的な行動をとることが求められたことが挙げられます。そこで、EUは、2030年までにGHG排出量を1990年と比べて55%減らす野心的な目標を掲げ、EU ETSは、この目標達成に大きな役割を果たし排出量の削減に向けて大きく貢献しています。
そして、より少ないコストで必要なGHG削減を達成するためにEU ETSを改善、対象範囲を海運業界まで広げたことで、2030年までに2005年度比の62%減らすという新しい目標を設定され、排出量の上限がさらに厳しくなりました。
出典:European Commission『Development of EU ETS (2005-2020) 』
出典: European Commission『Our ambition for 2030 』
日本企業への影響
日本では、カーボンニュートラル実現に向けた取り組みとして、グローバル市場で強い立場を確保し、環境保護に努めるとともに、GHG排出を減らすことを目標とする企業の集まり「GXリーグ」を設立しました。そして、日本でGHG排出量の約40%を占めるこれらの企業は、EUの環境基準に近いレベルで環境保護に貢献しています。
また、政府は、EUと同じレベルのGHG排出量を対象とした試験的な排出取引制度を導入し、化石燃料に課税することでGX投資を加速させようと考えています。これは、日本の企業に、EUのようにGHG排出量を制限するための市場アプローチを試み、化石燃料の使用を減らすために税金を課すことで、よりクリーンなエネルギーへの投資を促すものとしています。
出典:内閣官房『我が国のグリーントランスフォーメーション 実現に向けて』p,5.32.( 2023/09/14)
2.EU ETSの取引方法
ここでは、EU ETSの取引方法や近年の排出権の価格の動向についてご紹介します。
排出権有償購入型による取引へ移行
EU ETSの取引方法は、政府が設定・管理を行う「排出権無償割当型」と「排出権有償購入型」があり、排出権無償割当型は、企業ごとに排出上限が決められており、その上限までの排出権は無料で与えられますが、もし超過してしまった場合は、余剰が生じた企業から必要分を買い取るものです。一方、排出権有償購入型は、企業ごとに全体の排出総量が決められており、企業は自社の排出量に合わせて、必要な排出権をオークションで購入するものです。特徴として、無償割当型では政府の収入を得ませんが、有償購入型では政府にオークションから収入が得られるため、2013年度からEU ETSは排出権有償購入型に変わりつつあります。
第4フェーズの排出量の設定の考え方
EU ETSは、キャップ・アンド・トレード制度を用いており、そのキャップ(排出総量)設定の考え方はステップに応じて変化し、第3フェーズからは、毎年少しずつ上限を下げていくことで、企業による排出量の削減を促しています。現在進行中の第4フェーズでは、2030年のGHG排出量を1990年の水準から最低でも40%削減することを目標とし、2022年度からは、2008年~2012年にかけての排出権の年間平均発行量を基準として、毎年2.2%の割合で排出量を削減する直線的な計画が進行中です。
最近の排出権価格の動向
EU ETSの価格は2018年から上がっており、2020年には、価格が20ユーロ~30ユーロの間で変動していましたが、EUがGHG削減目標を高く設定した2020年12月以降、価格はさらに上昇、2021年9月にはCO2排出1トンあたりの価格が60ユーロを超えました。
そして、2022年2月には97.51ユーロだった価格が、ウクライナの状況の影響で価格が大きく変動し、2023年2月には過去最高価格の100.34ユーロとなりましたが、その後価格は下落し、2024年2月は53.54ユーロまで落ち込んでいます。
出典:環境省『参考資料集』p,10.(2022/11/07)
出典:Statista『EU-ETSの排出権(EUA)先物価格 2023年 』(2024/03/21)
3.気になる今後のEU ETSの動向
最後に、今後のEU ETSの動向についてご紹介します。
今後のEU ETSの動向
現在、EU ETSは、排出権無償割当型と有償購入型を併用した形で運用されていて、多くの企業が有償購入型での取引を行なっている中、鉄鋼やアルミニウム製造などの排出量が多い企業には、無償で排出権が与えられることがあります。しかし、2026年度からは無償割当型を減らしていき、2034年度には無償割当型を完全に廃止して有償購入型だけの取引としていきます。
出典:環境省『参考資料集』p,13.(2022/11/07)
新たに海運部門が追加
EU理事会は、2023年4月に2030年までにGHGを1990年度比で55%以上削減する目標を達成するための政策パッケージ「Fit for 55」に基づく5つの新しい法律を導入、新たに海運部門が排出量削減の対象となり、今後、海運会社は自社の排出量に基づいて排出権を購入する必要があります。MRV海運規則により、5000トン以上の船は2024年度から排出量の40%がEU ETSに含まれ、2025年度には70%、2026年度には排出量の100%が含まれます。
一方、5000トン未満の一般貨物船は、2025年度からMRV海運規則に従う必要がありますが、その後、EU ETSに含まれるかの判断は、欧州委員会が2024年終わりまでに評価を見て決定します。
出典:独立行政法人日本貿易振興機構『EU、気候変動対策パッケージ「Fit for 55」の重要法案を正式採択(EU) | ビジネス短信 』(2023/05/12)
出典:独立行政法人日本貿易振興機構『欧州海運業界、EU ETS適用を歓迎もカーボンリーケージを懸念(EU) | ビジネス短信 』(2022/01/28)
新たなETS「ETS ll」の創設
欧州委員会は、「Fit for 55」の一環として、EUの各国の道路交通や建物の分野でのGHG排出量削減のための新しい取り組み「ETS ll」を設け、2030年度に2005年度比の43%削減を目標とし、これにより、EUの各国は努力分担規則に基づいて、より効果的に排出量を削減することが期待されます。
取引方法は、既存のETSとは別のオークションでの取引となり、2026年度には特別措置として割当量の130%が供給、追加された30%分は2028年度〜2030年度のオークション量から差し引かれます。また、オークションで得た収入の1.5億トン(CO2換算)分の収入は、イノベーション基金に割り当てられ、残りは各国加盟国に分配されます。
出典:環境省『参考資料集』p,15.(2022/11/07)
出典:独立行政法人日本貿易振興機構『欧州道路輸送関連3団体、新ETS案を歓迎も商用車への支援拡充訴える(EU) | ビジネス短信』(2022/01/17)
4.まとめ:EU ETSの知識を深め海外でも通用する環境貢献を目指そう!
EU ETSとは、EUが気候変動と戦うために始めた、世界で最初の国際的な温室効果ガスの取引制度で、その手法にはキャップ・アンド・トレードが導入されています。現在、取引方法として「排出権無償割当型」と「排出権有償購入型」が併用されていますが、今後、無償割当型を徐々に減らし、2034年度からは有償購入型のみ運用となります。また、さらなる環境貢献を目指して、新たな制度「ETS ll」の導入や海運部門の追加が行われるなど、今後のEU ETSの動向にも注目です。
日本でも、EU ETSの考えを基準とした排出取引制度が見込まれていることから、ぜひ、EU ETSの知識を深め海外でも通用する環境貢献を目指しましょう。