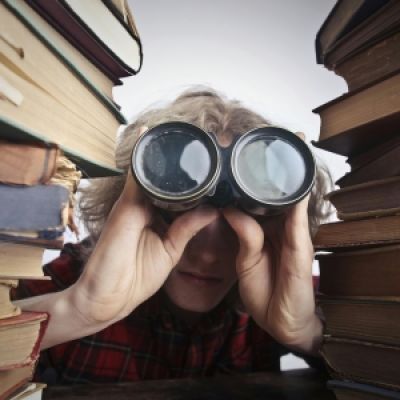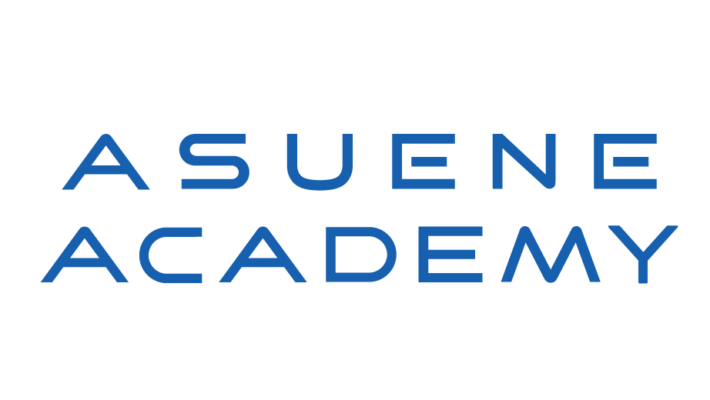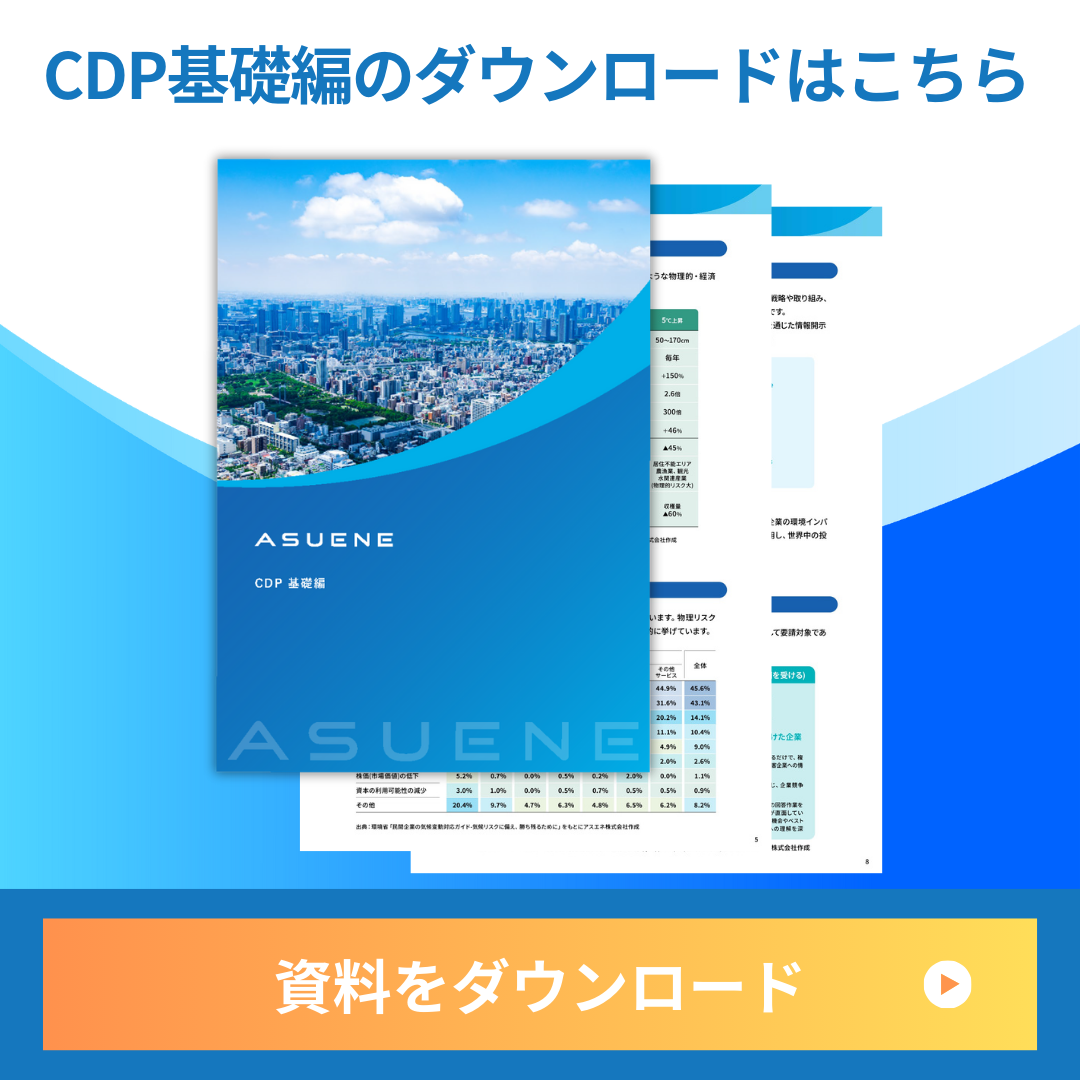「脱炭素に“触れ、学び、取り組む”ことで生活者の意識を変える第一歩を」をコンセプトに、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを行う「チャレンジ・カーボンニュートラル・コンソーシアム(以下、CCNC)」。買い物を通じて生活者のカーボンニュートラルな購買を促進するための実証実験、「みんなで減CO2(ゲンコツ)プロジェクト 触れて、学んで、取り組んで!誰でもできる減CO2行動で脱炭素!(以下ゲンコツプロジェクト)」を実施しています。
発起人である日本総合研究所の創発戦略センター グリーン・マーケディング・ラボ ラボ長/プリンシパルの佐々木努さん、グリーン・マーケティング・ラボ マネジャー 前田もと子さんに、生活者の行動変容と環境の取り組みにおける「売り上げ」について、お話を聞きました。
買い物を通じて、生活者の行動変容を起こす
ー CCNCではどのような取り組みをしているのでしょうか。
大きな目標として、脱炭素社会の構築の推進を掲げ、企業が自立自走的にカーボンニュートラルに取り組める仕組みを作っています。現在、企業はカーボンニュートラルに向けて、CO2の見える化など努力をしていると思います。
しかし、さまざまな企業にヒアリングをしてみると、脱炭素の取り組みとして環境負荷の少ない商品を販売しても、なかなか売り上げに直結しないという課題を抱えています。そのような状況下においては、企業がカーボンニュートラル達成まで持続的に取り組んでいくことはとても難しいのが実情ではないでしょうか。
その一方で生活者は、環境負荷が少ない製品よりも、価格の安いもの、いつも買いなれた商品に手が伸びがちです。環境に関しては、企業の取り組みと消費者の意識の間にギャップがあるのです。そこで、エンドユーザーのリテラシーを底上げし、環境負荷の低い商品により関心を持ってもらうことで、売り上げにつなげ、企業が自立自走的に脱炭素に取り組めるようにしたいと考え立ち上げたのが、CCNCです。2023年9月から活動をしています。とはいえ、1社のみの取り組みで、生活者の意識変容を起こすのはとても難しいことです。
そのため、商品を作っている製造業の企業と、商品を売る「場」を持つ流通業の企業と一緒に取り組むことで、サプライチェーン全体の脱炭素化を促進していきたいと考えました。
ー 参画企業を教えてください。
CFP算定をお願いしたアスエネのほか、発起人でコンサルティングの株式会社日本総合研究所、メーカーからはアサヒグループジャパン株式会社、サラヤ株式会社、三幸製菓株式会社、日本ハム株式会社、株式会社ユーグレナ、商品と提供する「場」である流通業として株式会社スギ薬局、株式会社万代、実際に削減する際のソリューションを持っているDaigasエナジー株式会社の計10社が参画しています。
― 同じ業界の企業が集まる団体ではない点が特徴的ですね。
はい。バリューチェーンをつなげ、サプライチェーンを上流から下流までつながないと、いま日本の企業が抱えている脱炭素の課題は解決できません。バリューチェーン、サプライチェーンの上流と下流を横断する組織をつくることは設立当初からのコンセプトでした。そして、「買い物」と「お金」「教育」の3つを活動の切り口に、まずは「買い物」から取り組みをはじめています。
――なぜ「買い物」から活動をはじめることにしたのですか?
「買い物」は生活者と企業を結ぶ接点です。普段の買い物のなかで、CO2排出量がより少ないものを選んで買ってもらうことで、製造している企業の努力が報われ、生活者はよりよい地球環境で暮らせるようになります。買い物の現場でカーボンニュートラル達成のための好循環を起こしたいと思っています。
――具体的な活動について教えてください。
スギ薬局3店舗と万代1店舗で、参画企業の商品を販売する実証実験、「みんなで減CO2(ゲンコツ)プロジェクト」を行いました。
販売するといっても、ただ店舗に陳列するだけではありません。CCNC参画企業のカーボンニュートラルに向けた取り組みや環境にいい商品などについてスマホアプリで楽しく学ぶことができる試みや、CO2を削減する行動を意識したアトラクションを実施するなど、買い物の現場で脱炭素について学ぶきっかけづくりを行いました。
――ゲンコツプロジェクトのキャラクターや仕掛けを見ると、今回の実証実験はお子さんがいる家庭をターゲットにしているのですか?
世代論を持ち出すのは適切ではないかもしれませんが、やはり若い世代の方が環境問題や気候変動に関心が高く、知識があるという事実があります。関心の高さや知識の有無が購買行動に直結するかどうかは別として、子ども世代によりよい地球を残すため、親世代が環境不可の少ない商品を選んだり、環境問題の知識がある子どもから促されて親が買い物したりすることが行動変容のきっかけになり得ると考えました。もちろんほかのアプローチ方法はあると思いますが、今回の「ゲンコツプロジェクト」は子どもがいるファミリー層をターゲットにしています。
子どもがいるファミリー層に商品を売りたい、環境への取り組みを知ってもらいたいと考えている企業の割合が高いことも、ターゲッティングに影響しています。もちろん、ほかのターゲッティングや切り口もあると思っていますが。

「環境にいい商品」だからこそ、売る工夫が必要
― 実際に実証実験を行ってみて、生活者の行動変容ができたと思われますか?
ここはとても難しい点だと感じています。
実証実験を行う前から、間違いなくわかっていたのは、脱炭素や環境に配慮している商品だとしても、生活者の約55%は行動を変えないということです。購買行動において価格を重視する、端的にいうと価格が安ければ買うというタイプの方たちが、この55%に含まれます。実際に実証実験でも、そのような結果が出ました。
もちろん、この55%の方たちも、もっとCO2の削減が進んだ社会になり、当たり前のように店頭にCFP算定がされた商品が並び、環境負荷が少ないものを選ぶ価値観が一般的になれば、購買行動も変容していくと思います。しかし現状は、大前提として、この55%はCCNCの活動のターゲットにならない層であると理解しておくことが重要だと考えます。つまり、今回のCCNCが行動変容を促したいターゲットは、残りの45%の人たちだということです。
結果的には、45%の人たちのなかには、きちんとCO2排出量を見える化して、CFPを算定した商品がほしい人もいました。もちろん、CFP算定の数字はまったく必要ないという人もいます。そういう人でも、今回の実証実験のように、娯楽性やエンタテインメント要素とともに学びのきっかけと商品を提供することで、購買行動を変える方もいらっしゃいます。
― 売り上げの変化はあったのでしょうか?
2024年1月から2月にかけて、約1か月の実証実験中に取り扱った参画企業の商品は、実証前と実証後を比較すると、実証展開していない近隣店舗に比べて約40%売り上げが上がったという結果が出ました。
CCNCの活動を通して、売り場をつくり、商品を露出して、生活者に興味を持ってもらうことで、実際に買ってもらうことができます。この活動を継続することが課題とは言えますが、「環境に配慮しているあの商品いいね、そういう商品を出している企業はいいね」と思ってくれたら、生活者が「とりあえず買ってみよう」と購買行動を変えてくれることは、今回の実証実験でわかりました。
また、従来とは異なるカテゴリーの売り場で陳列されたことにより、生活者の目に触れる「機会」が新たに生まれることもわかりました。
例えば、通常であれば飲料の売り場に置かれているアサヒのシンプルecoラベルのミネラルウォーターは、今回の実証実験では、サラヤの「ヤシノミ洗剤」の横に環境に配慮した商品として陳列されました。「ヤシノミ洗剤」を普段から利用しているお客様が、いつもならば気にかけることがなかった、アサヒのシンプルecoラベルのミネラルウォーターを環境にいい商品として、新たに「認知」して、購入するといったことが起きたのです。そのほかの商品においても同様のことが言えます。
これは今回の実証実験だからこそ起きた、行動変容の一例だと思います。
― 価格重視の生活者に対し、環境に配慮した商品に興味をもってもらう工夫はどのようにすればいいと思われますか?
買い物といっても、その購買行動にはさまざまな形態があります。例えば今回はスーパーマーケットの万代とドラッグストアのスギ薬局で実証実験を行いましたが、スーパーとドラッグストアでは、そもそも買い物の目的が異なります。
ドラッグストアは買い物の目的、商品が決まっていて足を運ぶ方が多いのに比べ、スーパーマーケットは献立を考えながらなど、買う商品を限定的に決めずに訪れる方が多いことが特徴です。買い物の目的が異なれば購買行動も異なるのは当然です。どんな売り場なのか、その売り場を訪れる人の目的なども考慮に入れた施策を展開することはとても重要だと考えています。
また、環境に配慮した商品ならではのきめ細やかなマーケティング施策も重要だと思っています。一般的に、商品を発売する際には、「こういう商品だから」「こういうターゲットに向けて」「こういう訴求をしていこう」とかなり細かく施策を検討してマーケティングを行います。ところが環境配慮型の商品になると「環境にいい商品なのだから、買ってほしい」といったように大まかな施策に陥ってしまう傾向にあります。環境へのよさをアピールすることだけに終始してしまうのです。
「環境にいい商品だから」ではなく、環境にいい商品を、「どういう層に」「どのように訴求していくか」を考えるべきです。環境負荷が低いことを含め、その商品のよさを細分化してマーケティングし、生活者に訴求していく必要があるのではないでしょうか。売り場における生活者と企業のコミュニケーションをもっと丁寧に構築していくことが大切です。

CFP算定にエンタテインメントを与える
― 実証実験を経て、今後の展望を教えてください。
今回の実証実験で、教育の重要性を痛感しました。売り場で環境問題や気候変動の教育を行い、その場で行動変容を起こすには限界があります。
そこで2024年度には、教育の現場や自治体などと連携し、生活者に、お店へ来る前の段階で環境問題やCFP算定についての意識を高めてもらう活動を行っていく予定です。お店に足を運んでもらう前の教育啓発と、売り場での購買行動をシームレスに繋いでいくことに注力していきます。生活者が学んだことをお店で実践できるように促していきます。
そうすることによって、メーカーと小売りの現場でできないことが実現できるようになり、生活者の行動変容を促進することにつながりますから。
― 買い物という誰もが経験する日常の行為を通じての行動変容だからこそ、その活動は多様なものになりそうですね。
たとえば、エコラベルは色々な種類が多種多様な商品に貼付・表示されていますが、それを気にして買い物をしている生活者は多くはありません。子どもたちに「エコラベルを探そう」と訴求するエンタテインメント性のある仕掛けを行ったところ、家の中や売場で宝探しのように探してくれるようになりました。それを見た保護者の方も一緒になってエコラベルを探し、買い物のときに意識するようになりました。これはまさに習慣化であり、行動変容です。
私たちはCFP算定もエコラベルの例のように啓発していく必要があると思っています。生活者のみなさんにCFP算定の数字が書かれた商品を探してもらうといった仕掛けをすることもひとつの方法だと思います。現在ではまだCFP算定を実施している商品がレアなので、売り場で探す楽しみを提供することができます。企業にとっては、先んじて算定を行うメリットにもなっていくでしょう。
「アスエネ」のようなシステムを使って、信頼性の担保されたCFP算定を行い、それをエンタテイメントとともに届ける。そうすることで、新たな購買層の開拓にもつながるはずです。信頼性のある算定、取り組みを行うことで企業が自社の活動をPRする機会も増えると思います。
ー その結果、より生活者にCFP算定された商品が身近なものになっていくのではないでしょうか。
そのためにも、CCNCの参画企業も増やしていきたいです。
現在、当社を含めて10社でCCNCの活動を行っていますが、参画企業の裾野を広げていくことも計画しています。初年度の活動に参画してくださった企業の皆さんには、試行錯誤にお付き合いいただき感謝しています。引き続きともに生活者の行動変容を促していきたいです。ただ私たちの目標である「脱酸素社会の構築」は10社だけで実現できるものではありません。より多くの売り場で、より多く環境にいい商品を陳列・販売することが、生活者の行動変容を促進します。多くの企業に参画していただくことで、それが実現するのです。
今年(2024年)には大いに店舗数を増やして、実証実験を行う予定になっています。サプライチェーン全体でカーボンニュートラルを目指すCCNCの活動にぜひ多くの企業に参画していただきたいです。